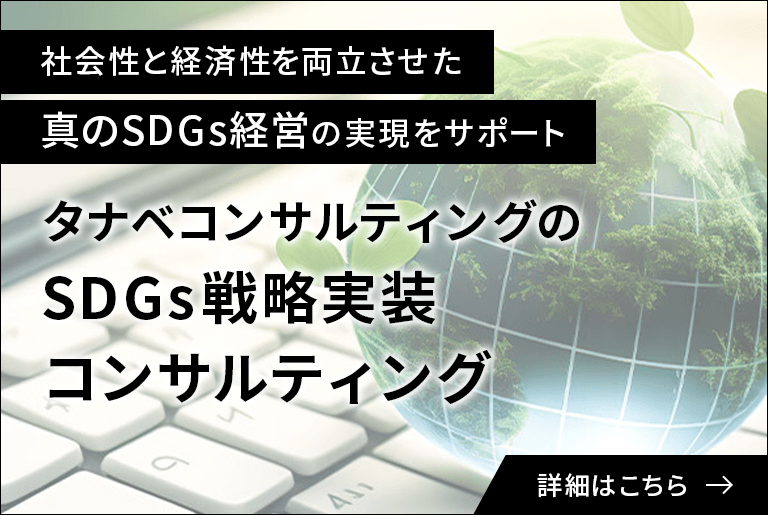COLUMN
コラム
閉じる
SDGsに取り組んでいることをアピールしている企業が増えている中、そのうち実態が伴った取組みをしている企業はどれくらいいるだろうか?いわゆる"SDGsウォッシュ"が抱えるリスクとそうならないための対策を考えていきます。
SDGsウォッシュはリスク
SDGsウォッシュが抱えるリスクとは
2015年にSDGsが採択されてから、現在になってようやく国民の知名度も高まり、関心を持つ人が増えてきています。併せて、SDGsに取り組んでいることをアピールしている企業も増えています。しかしながら、HPでの発信や名刺にロゴを掲載したり、バッジを付けたりしているものの、自社の取組みと17のゴールを関連付けただけで終わっており、肝心の取組み実態がない上辺だけのSDGsになっている企業も少なくありません。
例えば、「天然素材」「リサイクル素材」で作られている衣服をアピールしているアパレルブランドが、実際には製造過程で通常より多くのCO2を排出していたり、発展途上国で雇用創出をしているとアピールしながら、実際は低賃金で過酷な労働を強いているなどが挙げられます。
こういったSDGsウォッシュは、事業面にも経営面にも大きな影響を及ぼします。実態が伴っていないことが見透かされるとステークホルダーからの信頼が失われ、企業イメージの低下に繋がります。そうなると、投資機関からの融資に影響したり、取引先からの取引停止になることも考えられます。また、一般消費者のSDGsへの関心も高まっているため、SNSでそのようなイメージが拡散されると業績にも大きな影響が生じてしまいます。
なぜSDGsウォッシュに陥るのか?
なぜSDGsウォッシュに陥る企業が多いのか、その要因は大きく以下3点と考えられます。
1.サプライチェーンの管理・実態把握が出来ていない
最終製品や完成品の品質と価格の両面にこだわるあまり、サプライチェーン全体の管理が不足してしまうことにより先述した事例のような事態が起こる可能性があります。17のゴールのうち、ある特定のゴールのみに捉われず、全体を俯瞰して何が最適かをよく設計する必要があります。
2.コミュニケーションエラー・誇大広告
実態を把握していないことによる事実と異なる内容の発信、事実を誇大した大げさな広告、曖昧な表現による誤解、などコミュニケーションの間違いからSDGsウォッシュになるケースもあります。
3."SDGs"というイメージの先行
ここ数年で「SDGs」というワードが一般にも認知されてきました。「SDGsは何か社会や環境に良いことなんだ」というイメージが広まり、企業側も「わが社も何かSDGsに取り組まなければ」という意識が先行してしまっているように感じます。そのため、実態が追い付いていなく、事業と関連付けただけの"なんちゃってSDGs"が生まれてしまっていると考えられます。

SDGsウォッシュと指摘されうる例
アパレル製造業に多い例
発展途上国の強制労働に加担しているとみなされる例が多いです。特に、アパレル業界では生産地として、労働力があり賃金が安い東南アジアエリアに移っており、その労働環境の管理、不透明性から問題が起こっています。直接的に加担していなくても間接的に関わっている危険性もあり、生産工程における労働環境の透明性がきわめて重要であります。
海外下請け工場の労働問題はたびたび話題になっており、人権問題の1つとして世界的にも注目されています。
企業として発信している内容と実際の環境にずれが生じる可能性として、広報は広報部門、生産管理は生産管理部門と独立しており、社内での情報共有やコミュニケーションが十分に図れていないことがあげられます。これはどの企業でも起こりえる問題です。
医薬品メーカーに多い例
肌を白く見せるなどの商品は多く存在します。しかし「Black Lives Matter」というフレーズが記憶に新しいように人種差別の問題や多様性を認める風潮はますます強くなっています。
そういった中で多様な肌の色を認めながら、美白・色白を美化するといった企業姿勢に批判が起きる可能性もあります。何が本質的に重要なのかをしっかり理解し、正しい取り組みを正しく発信することが重要となります。
SDGsウォッシュを避けるために
コミュニケーション
コミュニケーションの取り方には細心の注意を払わなければなりません。SDGsウォッシュにならないためには、
①本質を捉えた取り組みを行い正しく発信する
②誇張したり拡大解釈した表現は避ける
③定量化など実態が伝わる工夫を行う
など、コミュニケーションの基本に則った情報発信を心がければ、SDGsウォッシュと指摘されるリスクは大幅に軽減できます。
SDGsを目的化しない
SDGsウォッシュに陥っている企業の多くが、「SDGsに取り組むこと」が目的になってしまっていることが挙げられます。取り組みそのものはプロセスでありゴールではありません。
まず、企業・全社員がSDGsを正しく理解することから始めることが望ましいです。全員が同じ理解・認識を持ってから具体的なSDGsの取組みを設計しましょう。
そして、手段(プロセス)が目的にならないためには、明確な目標を掲げる必要があります。17のゴールに紐づけて
「●●の製造工程でのCO2排出量を2030年までに▲▲%削減する」
「2030年までに●●の生産に使用される××素材の▲▲%をリサイクル素材に置き換える」
など、具体的に期限と目標数値を設定することで、社内外に対する取組みの理解・信頼を得ることに繋がります。
更に、その目標実現のためのアクションまで設計し、経営計画・事業計画にまで落とし込んでいきましょう。
目標設定には、「アウトサイド・イン・アプローチ」が推奨されます。「アウト=社会」から「イン=企業・組織」、つまり「社会課題の解決から自社の目標に落とし込む」アプローチです。
これからのビジネスは社会性も重要視され、SDGsウォッシュにならないためには、収益だけでなく社会性も目的としたビジネスに思考を切り替えていく必要があります。

著者
最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト