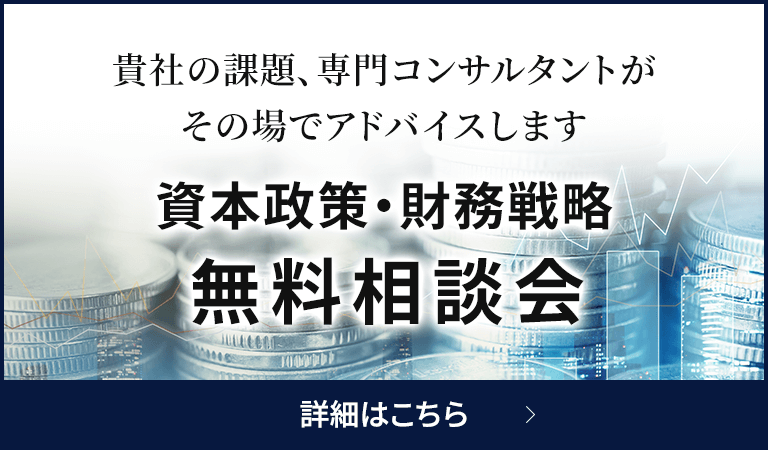効果的なMBOスキームとは?
EXIT戦略を成功に導く7つのステップ
- 資本政策・財務戦略

閉じる
近年、上場廃止を選択する企業が増加しています。2025年上半期の上場廃止件数は59社に達し、前年の51社から8社増加しました。この数字は、データを遡れる2014年以降で最も速いペースとなっています。年間で最多だった2024年の94社を上回るペースとなっています。特に注目すべきは、MBOによる非上場化の増加です。2024年に上場廃止となった94社のうち、20社がMBOを通じて非上場化を選択しました。
効果的なMBOスキームによるEXIT戦略に向けた要諦
MBO実施が増加している背景
MBO(Management Buyout)とは、企業の経営陣や従業員(MEBO:Management and Employee Buyout)が自社を買収する手法を指します。その主な目的は以下の通りです。
①株式の非公開化を選択し、経営の自由度を高める。
②短期志向の株主投資に対し、経営陣が株主主体となることで中長期的な成長を目指す。
また、非上場企業においては、事業承継対策を目的としたMBOの実施が増加しています。
MBOが全体的に増加している背景として、以下の要因が挙げられます。
①東証の上場基準の厳格化、開示義務の増加、資本効率改善要請、株主からの圧力の高まり。
②プライベートエクイティファンドやアクティビストの活動増加。
③相続対策スキームとしての活用。
MBOは企業買収の一手段であり、その目的は資本政策や非上場化など多岐にわたります。企業の主要所有者(筆頭株主)を新たに定め、所有と経営を一致させることで、経営陣の自由度を高めると同時に、企業経営に対する責任を強化することが可能です。また、MBOの実施主体は経営陣や従業員の個人に限らず、持株会や組合、SPC(特別目的会社)を活用するスキームも存在します。一言でMBOといっても、その実施スキームは多岐にわたります。本コラムでは、目的に応じた効果的なMBOスキームを、検討ステップに沿ってご紹介します。
効果的なMBOスキーム:7つのステップ
MBOを実施していくにあたり、7つのステップを押さえて検討を進めることが重要です。
①目的の明確化
②資金調達計画
③企業価値の算定
④法的・税務的観点の検討
⑤新経営陣の役割や責任の所在の明確化
⑥ステークホルダーや従業員への影響と配慮
⑦実行計画の策定
これらステップに分けて、MBOの実施を検討します。
また、実行後の組織設計や戦略策定も重要な検討事項でありますが、今回はMBOフェーズに焦点を当て、各ステップの要点について解説します。
まず最初に重要なのは、「①目的の明確化」です。MBOを成功させるには、その選択理由を明確にし、適切な手段であるかを再確認することが重要です。
例えば、以下のような目的が考えられます。
・上場廃止を通じて、中長期的な経営を目指す。
・事業承継の一環として、資本政策を実行する。
・非上場化による買収防衛を図る。
・経営陣のモチベーション向上を図る。
これらの目的に応じて、MBO以外の代替手段も存在する場合があります。
そのため、目的を達成する上でMBOが最も効果的な手段であるかを慎重に検討することが重要です。
MBO実施を決定した後、次のステップとして「②資金調達計画の立案」が重要となります。
これは、MBOの実現可能性を判断するためのプロセスです。
経営陣が自己資産のみで株式を買い取れるケースは少なく、多くの場合、外部からの資金調達が必要となります。例えば、プライベートエクイティ(PE)と連携する手法があります。この場合、プライベートエクイティが株式の大半を取得し、残りを経営陣に割り振るケースが一般的です。この手法では、買収後に企業価値を高めて再上場し、キャピタルゲインを得ることが目的となります。
また、銀行借入を活用する方法もあります。この場合、自社のバランスシートを毀損しないよう、SPC(特別目的会社)を設立して資金調達を行い、その資金で自社を買収する手法が取られることがあります。SPCを活用する目的の一つは、個人ではなく、法人として資金調達を行う点にあります。将来的には本社とSPCを合併させ、一つの会社に戻すことも可能です。
資金調達の目途が立った後は、「③企業価値の算定」を行います。企業価値の評価方法にはさまざまな種類がありますが、ここでは割愛します。
企業価値が確定したら、売買価格と照らし合わせて税務上の問題がないか、税負担がどの程度になるかをシミュレーションし、精査します。同時に、買収スキームが法的に問題ないかも確認する必要があります。
その後、より具体化のフェーズに進み、「⑤新経営陣の責任の所在」を明確にします。これにより、買収後の組織内での役割分担を明確化し、コミュニケーションの円滑化を図ります。株主構成の変更による現場従業員への影響は限定的ですが、従業員の不安を解消するためにも、MBOの目的や狙いをステークホルダーに説明し、理解を得るプロセスが必要です。
最後に、これまでの「①~⑦のステップ」をアクションプランに落とし込みます。具体的には、いつまでに何を行うか、行政や専門家(士業)からどのタイミングでアドバイスを受けるかを明確にし、全体の計画をまとめます。この推進体制を整えることが、実行フェーズにおいて非常に重要です。
最後に:MBOスキームにおけるEXIT戦略
最後に、MBOを活用したEXIT戦略についてご紹介します。MBOの目的によって、適したEXIT戦略は異なりますが、今回は事業承継対策を目的としたMBOを活用したEXIT戦略に焦点を当てます。
特に非上場企業で、相続税評価額が高い場合、経営者が過半数の株式を保有していると、相続税額が大きくなる懸念があります。このようなケースでは、MBOを資本政策の一環として活用することが可能です。一般的に、相続や贈与による税額は住民税を含めて最大55%を超えることがありますが、株式の売買では売却益に対して、「(売却額-取得費)×20.315%」の税金が課されるため、税負担を軽減する手段として有効です。具体的には、新たに法人(ホールディングスやSPC)を設立し、その法人の株主や経営者に新たな経営陣を置くことで、実質的に株式を新たな経営陣へ売却する形を取ります。この際、資金調達が必要となり、銀行からの調達を行う場合には、既存企業の収益性や信用力、担保余力などが重要な条件になってきます。さらに、役員持株会を活用することで、より多面的なMBOの実施が可能です。一言でMBOといっても、その活用方法は多岐にわたります。事業承継や資本政策の目的に応じて、最適なスキームを選択することが重要です。
関連記事
-

組織活性化の手法や生産性を高める実践ステップ
- ホールディング経営
-

企業が行うIR活動の目的と効果を発揮する施策とは
- 企業価値向上
-

ROICを浸透させるためのポイントを探る
- 資本政策・財務戦略
-

PBR向上の意義とPERとの違いを解説
- 企業価値向上
-

ROE ~ 企業価値向上における枢軸
- 企業価値向上
-

-

組織再編の目的や手法、実施する際のポイント
- グループ経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト