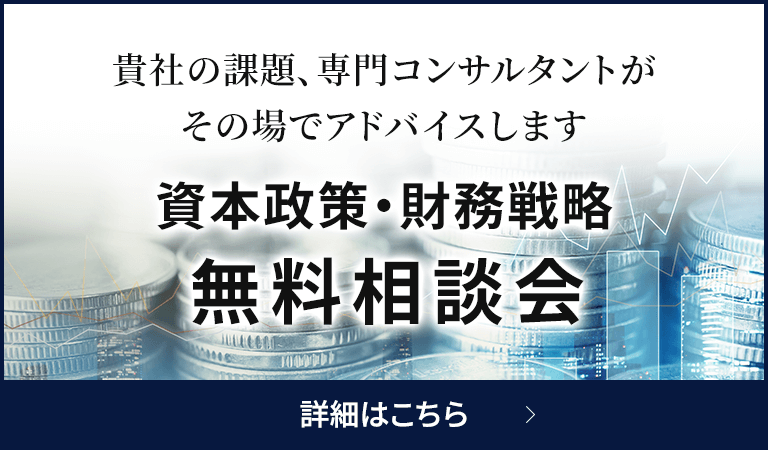ROICを浸透させるためのポイントを探る
- 資本政策・財務戦略

閉じる
2015年に導入された「コーポレートガバナンス・コード」や、2021年に改訂された同コードでは、企業に対して「資本コストを明示し、それを上回る収益性の確保」が求められるようになりました。資本コストを意識した経営が求められる中で、ROICが企業価値向上の鍵として注目されています。ROEでは把握しにくい実態を明確に把握でき、事業ごとの資本効率を評価するのにも適しています。
ROICとは?~ROAやROEとの違いを解説~
ROIC(Return on Invested Capital:投下資本利益率)とは、企業が調達した資本をいかに効率的に活用し、利益を生み出しているかを示す指標です。具体的には、「税引後営業利益(NOPAT)」を「投下資本(有利子負債+株主資本)」で割って算出されます。ROICは、企業全体の資本効率を測るため、経営者が資本コストを上回るリターンを出しているかを判断するのに有効です。
一方で、ROE(Return on Equity:自己資本利益率)は、株主が出資した自己資本に対してどの程度の利益を創出しているかを示す指標で、「当期純利益 ÷ 自己資本」で算出されます。ROEは株主視点での収益性を測るため、投資家にとって重要な指標ですが、財務レバレッジ(借入)を活用することで数値を高めることが可能であり、実態を正確に反映しない場合もあります。
また、ROA(Return on Assets:総資産利益率)は、「当期純利益 ÷ 総資産」で求められ、企業が保有するすべての資産をどれだけ効率的に活用して利益を上げているかを示します。ROAは企業の総合的な効率性を測る指標ですが、資本構成(自己資本と負債の比率)を考慮しないため、資本コストとの比較には適していません。
これら3つの指標はそれぞれ異なる視点から企業の収益性を評価しますが、近年、特にROICが注目されている背景には、資本コストを意識した経営が求められていることがあります。企業は、資本コスト(WACC)を上回るROICを実現することで、真に価値を創出していると評価されます。また、ROICは事業単位での算出が可能であり、事業ポートフォリオの見直しや資本配分の最適化にも活用できます。
さらに、東京証券取引所がPBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業に対して改善を促す中で、ROICを高めることが企業価値向上の鍵とされ、経営指標としての重要性が高まっています。ROICは、経営者と投資家の共通言語として、今後ますます重視される指標といえるでしょう。
ROICが浸透しない要因とは?
資本コストを上回るROICを実現することは、企業価値の向上に直結するため、近年、多くの企業で注目されています。しかし、実際にはROICが社内に十分に浸透せず、形式的な運用にとどまるケースも少なくありません。その背景には、いくつかの共通した課題があります。
第一に、ROICという指標自体が抽象的で分かりにくいという点が挙げられます。営業利益や売上高といった馴染みのある指標と異なり、ROICは「税引後営業利益」や「投下資本」といった専門的な概念を含むため、現場の社員にとっては理解しづらい傾向があります。特に、製造現場や営業部門など、日々の業務が数値管理と直結していない部門では、「なぜこの指標が重要なのか」が理解されず、納得されにくい傾向があります。
第二に、ROICは全社的な視点での指標であるため、個々の部門や社員の行動と結びつきにくいという問題があります。たとえば、ROICを高めるには利益率の向上や資本の効率的な活用が必要ですが、それを現場レベルでどう実行すればよいのかが明確でないと、具体的なアクションにつながりません。ROICを「営業利益率 × 投下資本回転率」に分解し、KPIとして落とし込む工夫がなければ、単なる経営層の指標として終わってしまいます。
第三に、部門別のROIC算出が難しいという実務的な課題もあります。ROICを部門単位で算出するには、共通費や資産の配賦、運転資本の管理など、精緻なデータとルールが必要です。これらが整備されていないと、部門ごとのROICが不正確になり、評価や意思決定に活用しづらくなります。結果として、ROICが経営会議での報告資料にとどまり、現場の改善活動には結びつかないという事態が起こります。
さらに、経営層自身がROICを十分に理解し、活用できていないケースもあります。ROICを掲げてはいるものの、実際の経営判断や投資判断においては従来の売上や利益重視の考え方から脱却できていない場合、社員にもその姿勢が伝わり、指標としての信頼性が損なわれてしまいます。
最後に、社内コミュニケーションの不足もROIC浸透の妨げとなります。ROICの意味や重要性、改善の方向性を、経営層から現場まで一貫して共有する仕組みがなければ、社員の理解や納得感は得られません。特に中小企業では、教育や情報共有のリソースが限られているため、意図が伝わらないまま、形だけの導入に終わることもあります。
ROICを真に経営に根付かせるためには、指標の分解とKPI化、教育の徹底、部門別の見える化、そして経営層の本気度が不可欠です。
ROICを浸透させるためのポイントとは?
ROICを社内に浸透させるうえで、まず重要なのは「現場の言葉」へと翻訳し直すことです。例えば、オムロンでは、ROICを「営業利益率 × 投下資本回転率」に分解し、それぞれをさらにKPIに落とし込む「ROICツリー」を導入しました。これにより、現場の社員が「自身の業務がROICにどう影響するか」を具体的に理解できるようになり、改善活動が自発的に生まれるようになったとされています。
次に、部門別ROICの「見える化」も効果的です。ある製造業の中堅企業では、各事業部ごとにROICを算出し、月次で経営会議に報告する仕組みを導入しました。これにより、資本効率の高い部門と低い部門の差が明確になり、経営資源の再配分や事業ポートフォリオの見直しが進みました。特に、ROICが資本コストを下回る部門に対しては、改善計画の提出を義務付けることで、経営の質が向上したとされています。
また、ROICを「評価制度や報酬制度」と連動させることも、浸透を促す有効な手段です。あるグローバル企業では、経営幹部の業績評価にROICを組み込み、報酬の一部を連動させました。これにより、短期的な利益追求ではなく、資本効率を意識した中長期的な経営判断が促されるようになりました。
さらに、社内教育やコミュニケーションの徹底も欠かせません。特に、経営層が自らの言葉でROICの意義を語り、現場との対話を重ねることが、浸透の鍵となります。
最後に、ROICを「経営の共通言語」として定着させるには、継続的な運用と改善が必要です。初期段階では数値の精度や配賦ルールに課題があっても、運用を通じて徐々に制度を整えていく姿勢が重要です。
ROICを単なる指標ではなく、経営と現場をつなぐ「行動の指針」として活用することが、真の浸透につながるのです。
関連記事
-

組織活性化の手法や生産性を高める実践ステップ
- ホールディング経営
-

効果的なMBOスキームとは?EXIT戦略を成功に導く7つのステップ
- 資本政策・財務戦略
-

企業が行うIR活動の目的と効果を発揮する施策とは
- 企業価値向上
-

PBR向上の意義とPERとの違いを解説
- 企業価値向上
-

ROE ~ 企業価値向上における枢軸
- 企業価値向上
-

-

組織再編の目的や手法、実施する際のポイント
- グループ経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト