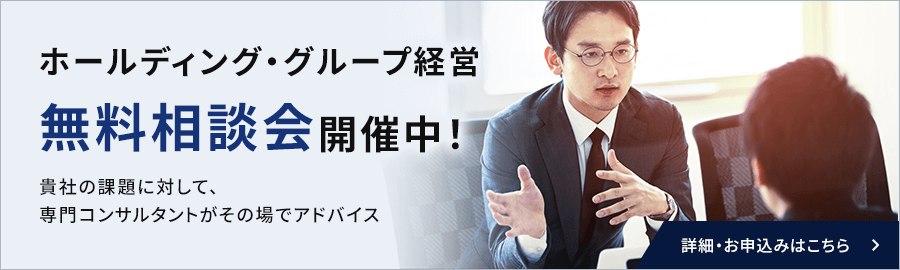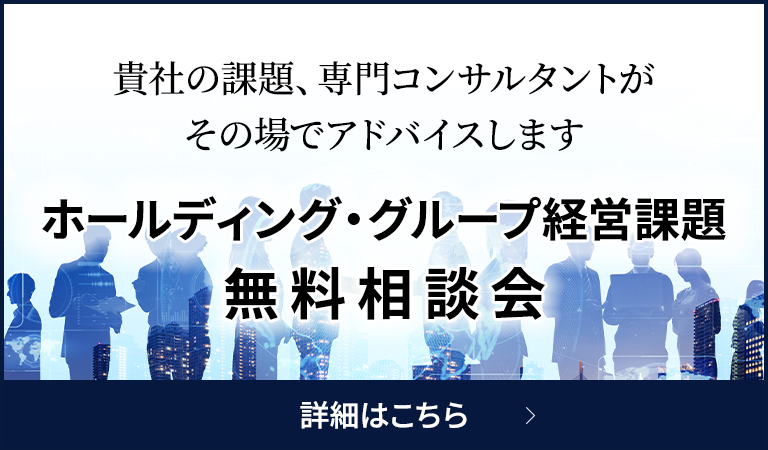なぜ、組織的経営が企業に必要なのか?
- グループ経営
- ホールディング経営
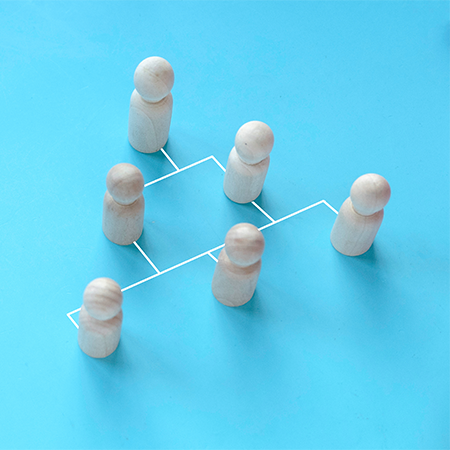
閉じる
昭和や平成の時代には、卓越したセンスやリーダーシップを持つカリスマ経営者が企業の成長を牽引するケースが多く見られました。しかし、現代ではビジネス環境の複雑化により、個人の能力に依存する経営では対応が難しい場面が増えています。その結果、組織全体で知識やスキルを共有し、連携して課題を解決する「組織的経営」が求められるようになっています。本コラムでは、なぜ組織的経営が必要とされるのか、その背景と理由を解説します。
組織的経営とは何か
組織的経営とは、「企業や団体がその目的を達成するために、明確なルールや適切な権限移譲に基づき、経営トップに限らず他のメンバーの知識や経験を活用し、部門間の連携や情報共有を通じて経営するスタイル」を指します。
カリスマ的経営とは、組織的経営の対照的な経営手法であり、「卓越した判断力やリーダーシップを持つ経営者に権限を集中させ、迅速な意思決定を行うトップダウン型の経営スタイル」を指します。一見すると組織的経営の方が優れているように思われますが、カリスマ的経営にも迅速かつ一貫性のある意思決定が可能であるなどのメリットがあり、事業の規模、従業員の成熟度、会社の成長度段階に応じて、どちらの経営スタイルを採用するかを判断する必要があります。
組織的経営の重要性
近年では、組織的経営を志向する企業が増加しています。特に中堅企業とされる規模の企業の多くが組織的経営を採用しており、その理由は主に2点に分けられます。
1つ目は事業承継です。高度経済成長期から約50年、バブル崩壊から約30年が経過しています。これらの時代は、市場の拡大にも支えられ、事業センスに長けたカリスマ経営者がいれば順調に業績を拡大することができました。そうした企業も創業から30年以上が経過し、事業承継期を迎え、ご子息やご息女へ代表を交代する中で、創業者のカリスマ的経営から組織的経営へと移行する企業が増えていると考えられます。
2つ目は時代の変化です。現代のビジネス環境はVUCA(不確実性や複雑性が高い状況)と呼ばれ、将来の予測が困難になっています。こうした時代背景で求められるのは、高度な専門性を活かした柔軟な対応力です。カリスマ的経営は、環境の変化が少なく、これまでの成功体験を活かせる状況では有効ですが、現在の事業環境ではその適用範囲が限定されます。
また、法令遵守やSDGsへの対応、ダイバーシティなど、企業が取り組むべき社会的テーマも、以前と比べて大幅に増加しています。こうした環境下で一人の優秀な経営者がすべての知識を兼ね備え、判断していくことが現実的に困難であり、組織的経営をとる企業が増えていると考えられます。
組織的経営のポイント
組織的経営を行う上で、重要なポイントは組織の本質が「統一」であるということです。組織経営に必要な要素には、目標設定、役割分担、コミュニケーション、意思決定、評価とフィードバックなどが含まれます。これらの要素が適切に機能することで、組織は効率的に運営され、持続的な成長を実現できます。つまりこれらの要素が有機的に結びつくことで、組織における「統一」が実現されるのです。経営学者の権威であるチェスター・バーナードは、自著の中で「組織は単なる人々の集まりではなく、共通の目標を持ち、それを達成するための協働システムである」と論じており、組織が成立するために必要な要素として、(1)共通目的(2)協働意欲(貢献意欲)(3)コミュニケーションの3点を挙げています。
(1)共通目的
組織で目標達成のために不可欠なのが、共通の目的を持つことです。経営陣や従業員など組織に関わる関係者全員が目的を共有し、その達成に向けて協働していくことが求められます。
共通の目的には、2つの側面があります。
1つ目は『協働的側面』です。これは、企業の理念やビジョンの実現に向けた協働を指します。
2つ目は『主観的側面』で、個人的な目的を指します。例えば、『家族のため』や『社会とつながりたい』といったものです。
(2)協働意欲(貢献意欲)
協働意欲とは、組織メンバーの共通目的を達成しようとする意欲のことをいいます。
昨今ではエンゲージメントや企業へのロイヤリティともいわれる考え方です。「この組織のために働きたい」「この組織に感謝している」「この組織の目標を実現させたい」などの気持ちが強いほど、組織力が強くなります。
協働意欲は、モチベーションと密接に関連しており、「誰かがやるだろう」「協力しても無駄だ」など、非協力的でモチベーションの低いメンバーがいると組織全体の力が弱まります。協働意欲の低下は、業務の進捗を遅らせ、生産性の低下を招くことは明らかです。
(3)コミュニケーション
コミュニケーションが欠如した組織では、トップの考えが末端まで共有されず、価値判断基準にぶれが生じます。また、コミュニケーションが不十分な場合、トラブルが発生しても発見が遅れ、対処が遅れることで被害が拡大する可能性があります。昨今では、心理的安全性という言葉が注目されており、自身の考えを抵抗なく発信できる組織の構築が求められています。発言しにくい組織は、従業員にとって働きづらい環境となり、業務の効率が低下するだけでなく、生産性の低下や離職率の上昇を招く可能性があります。企業は、従業員同士のコミュニケーションや部門間の壁を超えた連携を活性化させる必要があります。
これらに加えて、バーナードは組織内での「権威」と「インセンティブ」の重要性を強調しています。
「権威」とは、リーダーやマネジャーが指示を出す権力であり、その権力が部下から認められるほど効果を発揮します。
「インセンティブ」とは、目標を達成した際に得られる追加報酬を指します。これには、給与や昇進だけでなく、承認や評価といった非金銭的報酬も含まれます。組織目標への貢献を促すための動機付け手段として有効です。
まとめ
現代では、業種や業態を問わず、すべての企業がいずれ組織的経営に移行すると考えられます。カリスマ的経営が否定されるわけではなく、創業時には多くの企業がカリスマ的経営から始まります。企業の成長段階に応じて、トップが責任と権限を適切に委譲し、時代に即した組織的経営への移行が求められます。
また、各組織が抱える固有の課題を適切に把握し、それに応じた理論を柔軟に取り入れることで、より効率的かつ効果的な運営が可能となります。重要なのは、単に理論を導入するだけではなく、実際の業務や組織文化にどのように適合させ、持続的に改善していくかという点です。組織の主役はあくまで人です。組織で働く従業員が最大のパフォーマンスを発揮できるよう、真摯に向き合うことが重要です。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト