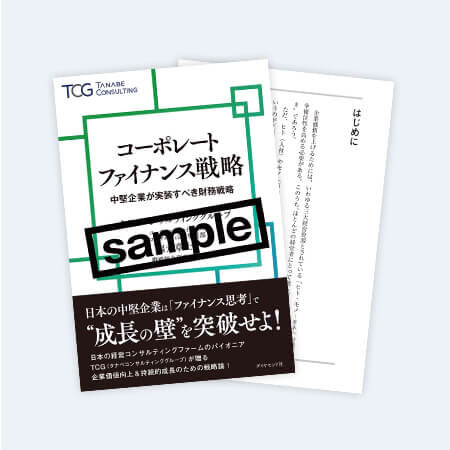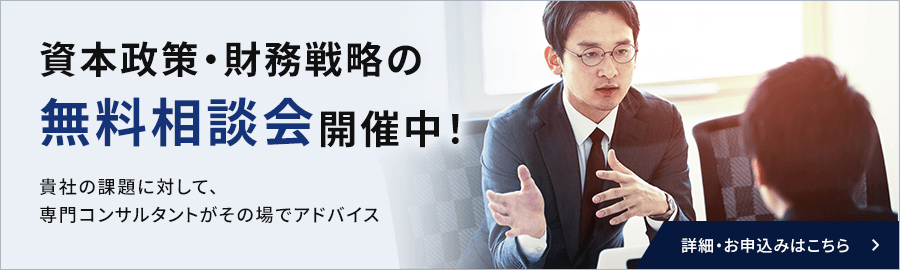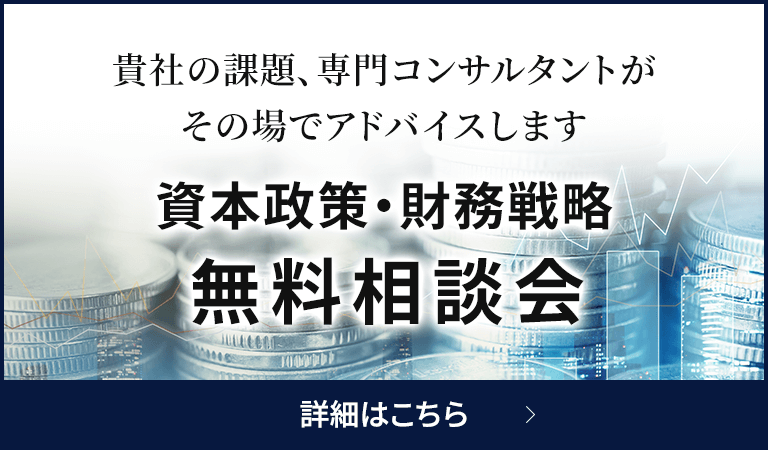中堅企業が実装すべき財務戦略
~企業価値を高める収益改善のポイント~
- 資本政策・財務戦略

閉じる
本コラムは、ダイヤモンド社発行の「コーポレートファイナンス戦略」の第2章の抜粋記事です。
3 企業価値を高める収益改善のポイント
企業価値を高めるためには、自社の収益構造を変えなければならない。そのために大切なことは、何をどう捨てるか、見直すかである。これまでの延長線上で収益改善を考えるのではなく、生産性が上がっていない中身を数字でしっかりと把握して、どのように改善するのか、また捨てるのかを決断しなければならない。
とはいえ、将来の成長に必要な投資は必要不可欠である。戦略コストとオペレーションコストを明確に区別し、戦略投資を行いながらオペレーションコストをいかに最小化するかのバランスが大切になる。
収益構造でカギを握るのは、売上げに対する限界利益の割合(限界利益率)と固定費の割合である。管理会計上では、当然ながら限界利益の割合が高く、固定費の割合が低いほうが高収益となる。したがって、自社の限界利益率がライバル企業のそれと比べてどのレベルにあるのか。固定費の割合、さらには人件費やその他固定費の割合が、ライバル企業と比べてどうなのかを正しく認識しておく必要がある。
限界利益率と固定費率(さらにはその細目)ともに事業別で比較分析ができれば理想的だが、限界利益率の事業別比較分析だけでも最低限、実施してほしい。そして、ライバルよりも限界利益率が低い場合は、材料費、外注費、物流費といった変動費の項目を細かく分析し、自社の限界利益率が低い原因を浮き彫りにしていく。
次に、自社が収益構造改革を進めるうえで必要な3つの着眼点について述べる。
1つ目は「今後の需要予測」である。もちろん、今後の見通しは不確実だが、自社の特定の製品・サービスや顧客別の需要を分析してみると、需要の不確実性は残るものの、ある程度は定量的に把握することは可能である。
2つ目が「原価コスト構造の見える化」である。需要リスクが予測できれば、そのリスクの悪影響を受けやすい原価コストの中身は何か、どの製品・サービスがリスクにさらされるかを把握しておく必要がある。
3つ目は、「高コスト要因の見える化」である。なぜコストが高いのか。その原因がわからずして対策は打てない。高コストの要因を解明することが必要である。
この3つの着眼で、自社の収益構造をあらためて検討してほしい。収益構造を変えるために目指すべき姿は、大きく2つある。
1つ目は「高付加価値(高粗利益)型収益構造の構築」、2つ目が「ローコスト型収益構造の設計」である。外部環境の変化が激しいなか、それぞれの収益構造をどのように構築していくべきか。次に、高収益を上げている企業の事例を中心に解説しよう。
(1) 高付加価値(高粗利益)型収益構造の構築
まず、玩具メーカーA社の取り組みについて紹介する。
国内の玩具業界は一般的に、少子高齢化の影響で将来的には衰退へ向かうとみられている。そうした状況のなか、A社は独自の市場を創造し、高付加価値を実現している。それは同社の営業スタイルに大きな要因がある。納入先に自社製品を売り込みに行くのではなく、納入先の要望をキャッチするためにきめ細かく訪問し、その要望に応えるオリジナル商品を生産する仕組みを構築している。それに加え、ただ商品化するのではなく、他社がまねできないほどの低価格で提供する。これは中国の生産協力工場とのネットワークを長年にわたり構築しているからこそできる仕組みである。さらには協力工場に対して品質面の技術指導も実施するなど、価格面だけの付き合いではない。このように販売から生産まで一貫した仕組みを構築することにより、高付加価値の収益構造を実現している。
同業他社の粗利益率が30%程度であるのに対し、A社では50%を確保できる収益構造となっている。きめ細かな営業活動などサービスを向上させることで、売上高経費比率は40%と同業他社(30%)より高水準にもかかわらず、それを上回る付加価値を確保できていることが、A社の競争力の源泉である。
もう1つの事例を紹介する。印刷会社B社の事例である。
かつて印刷業界は景気に左右されない業界として知られ、1991年のピーク時には出荷額が9兆円に達した。だが、その後はインターネットの普及や環境保護意識の向上により社会全体でペーパーレス化が進み、現在は出荷額が4.8兆円(2021年)と約半減した。マーケットサイズが縮小するにつれ、価格競争による収益悪化が顕著となっている業界の1つである。そのようななか、成長マーケットであるヘルスケア分野に特化することで高収益を上げているのがB社である。
B社は通常のチラシ印刷はいっさい手掛けずに、介護現場で使用する印刷物に特化することで差別化を図り、付加価値を高めている。つまり、ケアマネジャーやホームヘルパーが使う手帳から事業所で使用する帳票類まで、一貫して請け負うことで介護現場のニーズを細かく拾い、より使いやすい印刷物を提供しているのである。
現場で働く人たちに直接ヒアリングすることにより、自社の企画ノウハウとして蓄積し、横展開するスタイルで顧客を囲い込むビジネスモデルを構築。チラシ印刷を主に手掛ける他社の粗利益率が20%であるのに対し、B社は35%を確保している。
さらに事例をもう1社。建設会社C社は既存のビジネスモデルそのものを変更することで、低収益から高収益へと転換した企業である。
もともとC社は、地場の下請け建設会社として公共工事や民間の改修工事などを手掛けていた。しかしリーマン・ショック以降、売上げ維持のための採算割れ受注が続き、2期連続の赤字決算を余儀なくされた。この赤字の原因は、売上げの6割を占めるマンション施工事業が実質赤字になっていたことだった。
そこでマンション施工から撤退を決断し、改修・メンテナンス事業に特化した。マンション施工部門の人員は縮小して再出発し、売上げは3分の1程度に縮小したが、現在では経常利益率5%を確保するまでに回復した。自社の収益構造を見える化し、収益性の低い営業所、工場、エリア、顧客を選別することで収益構造改革を成し遂げたのである。
(2) ローコスト型収益構造の設計
人は腰の位置が高い姿勢だと、少しの接触でもバランスを失ってよろめきやすい。企業も腰が高いと、少しの減収で経営が不安定になりやすいものだ。この〝腰の位置〟を決めるのが「損益分岐点操業度」である。この数値が高い企業は、売上げが少し減るとすぐ赤字に転落してしまう。そんな赤字体質の企業に求められることは、とにかく腰を落とすことだ。損益分岐点操業度は70%以下に引き下げることが望ましい。
損益分岐点操業度を引き下げるためには、損益分岐点売上高を低くする必要がある。損益分岐点売上高とは収支トントン(利益ゼロ)のときの売上高である。ローコストの企業ほど損益分岐点売上高は低くなり、不況に強い経営体質を構築することができる。したがって、いかにコストを削減できるかが重要だ。
コスト削減のポイントは、変動費を比率で、固定費は金額で、どれくらい削減できるかを考えることである。つまり、変動費は売上げの増減と比例するため「率」でマネジメントし、固定費は売上げの増減に関係なく発生するため「額」でマネジメントするということだ。
このマネジメントを実施するうえで、参考になる事例を1つ紹介する。
電気機器メーカーのD社は、変動費と固定費のコストダウン活動を、それぞれの部署がバラバラに行うのではなく、全社員参加の下で実施している。ある部署だけの活動で終始するのではなく、トップが自ら1件1件の経費精算に目を通し、本気でコスト削減に取り組む姿勢を全社員に示している。また、全社員に対しても削減アイデアの提言を個人目標として掲げさせ、自ら実行する風土づくりにも注力している。
このように、新たな収益構造を構築して成長する企業は多い。ただ、実際はほとんどの企業が収益面での課題を抱えているのが現状である。
関連記事
-

組織活性化の手法や生産性を高める実践ステップ
- ホールディング経営
-

効果的なMBOスキームとは?EXIT戦略を成功に導く7つのステップ
- 資本政策・財務戦略
-

企業が行うIR活動の目的と効果を発揮する施策とは
- 企業価値向上
-

ROICを浸透させるためのポイントを探る
- 資本政策・財務戦略
-

PBR向上の意義とPERとの違いを解説
- 企業価値向上
-

ROE ~ 企業価値向上における枢軸
- 企業価値向上
-

-

組織再編の目的や手法、実施する際のポイント
- グループ経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト