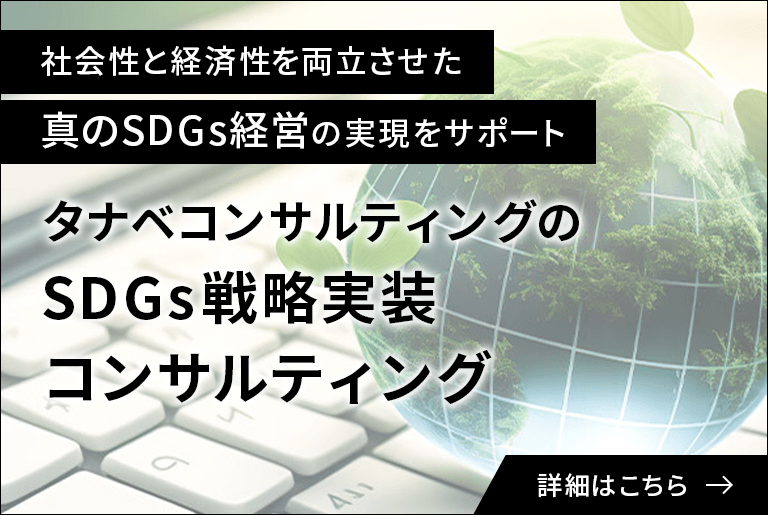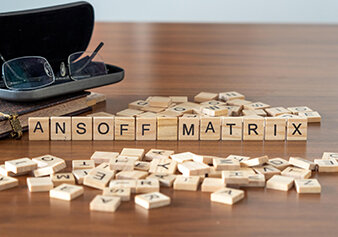COLUMN
コラム
閉じる
アパレル業界にとってSDGsは重要なテーマです。不良在庫の大量焼却や、不法労働、製造工程で発生する環境負荷など業界課題があります。全世界的な価値観の変容に対し、業界各社の対応が待ったなしの状況です。
アパレル業界における社会課題とは
アパレル業界における環境負荷の現状
アパレル業界における環境負荷の課題は生産した商品が売れ残ることによる大量廃棄があります。多くの企業は店頭に在庫がなくなることを回避するために低い消化率で生産計画を設計しています。その所以はSKU構造(Stock Keeping Unit)にもあるカラーバリエーションやサイズ展開に対してカラー切れやサイズ切れが起きないように生産をしているからです。その為、販売されない商品が発生しやすいという商習慣化しています。
現在ではアウトレットや不要在庫を買い取る業者が出てきていますが、それだけでは消化し切れていない状態です。また、アウトレットにおいても在庫切れが起きないように、プロパー商品とは別にアウトレット専用の商品を製造している会社も少なくありません。アウトレットはプロパーの売れ残り品を消化する場ではなくなってしまったのです。また、不要在庫の買い取り業者はメーカーや卸販売会社から低単価で大量に商品を買い取っていますが、業者の倉庫には行き先を失った商品の入ったダンボールが山積みになっています。その在庫の行く先は焼却されるか、海外にコンテナで輸送され海外で処分されています。
アパレル業界のこの悪しき商習慣はどのようにして生まれてしまったのでしょうか。それはアパレル業界の歴史を振り返ると見えてきます。
アパレル業界の歴史とファストファッションの台頭
国内のアパレル市場は1990年14.7兆円をピークに毎年減少し続け、現在は9兆円程度となっています。約30年で市場は40%減少したことになります。また、国内供給点数は1990年の20億点から30年後には35億点まで増加しています。この重要と供給のバランスの逆転が業界の悪しき習慣の根源となっています。
2000年に需要と供給バランスが逆転しました。この頃、アパレル業界には「ファストファッション」と言われるブランドが台頭し始めました。海外から参入してきたファストファッションは世界をマーケットに最新の流行を取り入れ、低価格でかつ短サイクルで大量の商品を生産・販売しています。
また、多くの方にファッションを楽しむ機会を提供しました。欲しくても買えなかった最新のファッションを誰でも楽しめる世界を創り出し、指示され全世界で店舗出店が拡大しました。しかし、それと同時に大量生産により需給構造の変化をもたらし、消費者の価値観を変化させてしまいました。

アパレル業界が取り組むべきポイント①
業界全体の連携による新たなエコシステムの構築
このアパレル業界における課題はメーカーだけでは解決できません。メーカー、卸売企業、小売企業が連携した取組みや仕組みを構築することが求められます。
経済産業省は2021年7月に「繊維産業のサステナビリティに関する検討会」でエコシステムとして「サーキュラー・エコノミ―」を提唱しました。サーキュラーエコノミーとは今迄の原材料から製品化し、使用され廃棄されるという「リニア・エコノミー(直線型経済)」から製品化、使用後の原材料へ再循環する「サーキュラー・エコノミー(循環型経済)」へ転換することが必要です。
環境負荷に対する取り組むべきポイントは自社だけではなく、他社との協業による共創です。原料・原材料メーカーから小売まで、サプライチェーン全体の共創体制により、廃棄される可能性ある製品を再資源化していく事が必要です。
原料・原材料メーカーであれば、再資源化を前提とした商品・製品の開発や廃棄される商品を再資源化する為の取り組みを他社と連携し実現を目指すなど各社が共創を前提とした商品開発を行う事が必要です。
供給過多の市場構造とデジタル化
先述しました通り、アパレル業界の市場は縮小しています。その所以は商品単価が減少している一方で供給量が増加しているという構造でした。日本の人口が減少している中で、供給量が増加してきたという背景があります。
大量生産・大量消費で構成されてきたアパレル業界の収益率は低迷し、そして世の中に不要となる商品を大量に生み出してきています。生産拠点は海外に移管され、より安く生産、仕入れる事ができなければ、競争が激化したアパレル市場では生き残れない市場環境となりました。その過程の中で不法労働や生産国の環境配慮に目を伏せてきてしまったのです。
アパレル業界は、適正な生産量が読みにくいという課題がります。低収益故にデジタルに対する投資もままならず、現状の課題に奔走している状態となり、生産に対するデジタル化は進んでいません。販売することに対するデジタル投資が先行し、根本的な課題解決に繋がっていない状態です。
業界を上げて取り組むべきポイントは生産に対するデジタル化です。いかに不要な在庫を生み出さず、売上・利益を生み出すか。その為のデジタル投資が重要となります。
アパレル業界が取り組むべきポイント②
デジタル技術を活用した適正在庫の把握と販売
生産におけるデジタル化が進まない背景には収益率の課題があるが、加えて適正在庫が把握できていないという課題があります。生産される製品の数は明確ですが、最終的にどの商品がどれだけ売れたのか、どれだけ残っているかを把握することは生産しているSKU数が膨大であることと生産、卸売、小売に分断しているサプライチェーン構造の課題もあります。
生産してる企業は最終的に自社の商品がどれだけ残っているか把握することが出来ないために、科せられたた売上目標に対して、前期と同様の販売による消化率を元に生産量を設計せざるを得ないという状態です。
この課題を解決すために現在導入が進んでいるRFIDがあります。自社の手を離れた商品が最終的に販売されたのかをサプライチェーン全体で共有し、最適な在庫を把握する仕組みが必要です。その為にも製造、卸売、販売が連携したデジタル化を目指すことが必要です。
しかし、RFIDの単価が高ため、大手のみの導入に留まっています。共同体を形成したデジタル化を実現することを大手だけではなく地域や業界団体が連携した組織を作ることが必須となります。
SDGsによる新たなイノベーションを
アパレル業界にとってSDGsは今までの業界の課題を直視する機会となりました。そして、その課題は深く業界に染みついた商習慣に対してメスをいれ、変化を余儀なくされています。しかし、多くの企業は対応に遅れているか取り組めていいない現状です。
SDGsは業界にとってマイナスと捉える事が多いですが、プラスの機会として捉え自社の変革をしていく必要があります。返照した価値観は元に戻りません。自社の強みを見つめ直し、変化する価値に新たな取り組みをしていきましょう。
現在、エシカル消費などアパレル業界に少しずつ浸透してきています。ムダな在庫を減らし、収益率を高め新たな価値を創造するサステナビリティビジョンを掲げましょう。足元の課題から目線を上げ、自社の2030年、2040年のありたい姿とつくりたい社会、世界を想像してみましょう。
2030年のアパレル業界のサステナビリティビジョンのポイントはイノベーションです。いかに業界の当たり前から脱却し、わが社の理念、使命を見つめ直し、ミッションの再定義をしていきましょう。

著者
最新コラム

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策

- 選択と集中戦略とは?メリット・デメリットと成功事例を解説

- 新規事業開発プロセスの全貌!成功へ導く戦略とは

- 新規事業はどのように評価すればいい?成功に導くための10の評価軸
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

- 海外展開における課題と新規の海外代理店開拓プロセス
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト