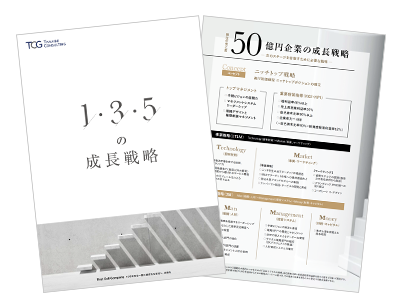COLUMN
コラム
閉じる

10年後の自社が顧客に選ばれる理由
あなたの会社に社会課題を解決する貢献価値は存在しますか?
「10年後の自社が顧客から選ばれるキーファクターは何でしょうか?」
キーファクターとは重要要素のことです。10年後の顧客から選ばれる重要要素は何だと思われますか?
これを考えることが企業のサステナビリティ経営にとって非常に重要な要素となります。
外部環境が変われば顧客から求められることも変わります。
実際、今回のコロナ禍において求められることが大きく変わったという企業も多いことでしょう。2019年に作った中期経営計画が全くその通りにならず見直しをしたということはよく聞きます。このように予想もしなかった外部環境の変化によって顧客から求められることが大きく変わることは今後は無いとは言い切れないでしょう。逆にこれほどのインパクトではないにしろ、必ず変化するものだと考えた方が良いです。
そのような不確実な世の中で一つ確かなものがあるとすれば、それは社会課題解決での貢献価値ではないでしょうか。
求められる製品やサービス自体は変化しても、そこに社会課題に対する貢献価値が存在するかどうかが最も重要な要素であり、社会課題に対する貢献価値のない商品やサービスはどのようなものであっても必要とはされない世の中になるでしょう。
社会課題解決による貢献価値を考える際に企業が取り組むSDGsが良い指標になります。SDGsは決して流行では片づけられないインパクトを持っています。
SDGsの本質が記載されている「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」にはこのような文言が記載されています。
「このような広範でユニバーサルな政策目標について、世界の指導者が共通の行動と努力を表明したことは未だかつてなかった。」
このようにSDGsは人類史上類を見ない規模の世界共通ビジョンであります。当然ながらここには多くのヒト・モノ・カネが集まり、企業にとっては成長のチャンスと言えます。
SDGsは社会課題解決による貢献価値を高めるための企業の羅針盤となり、新たな市場を開拓する方向性を示しています。
SDGsはあえて取り組むようなものではない。今やっていることがそのままSDGsだ。というお声をよく聞きます。しかし上手くSDGsを活用し10年後も持続的に企業価値を高められるように自社のサステナビリティへ積極的に取り組んでおられる企業が本当にたくさん存在します。そのような中でこれを活かさない手はないと考えます。今一度自社が取り組むSDGsにどのような意味があるのか、自社にとってどのようなインパクトがあるのかを正しく理解する必要があると考えます。
もし自社がそれに取り組まなければ圧倒的にイノベーティブな取り組みを行う新たなライバルが登場し、市場を席巻するその波にのまれてしまうでしょう。
そうなる前にこれらの波をチャンスと捉え"社会課題解決を軸とした事業戦略・経営戦略"を構築し、未来の貢献価値を創造するためのアクションを起こしましょう。
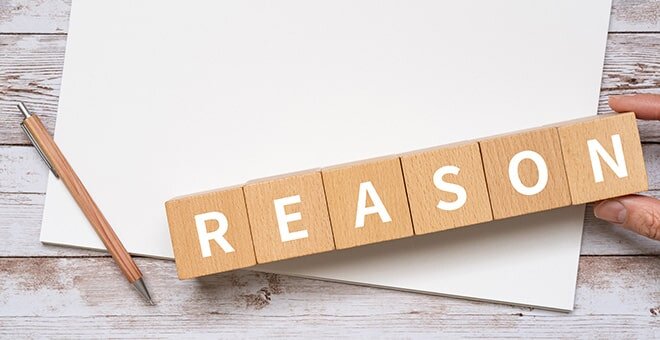
自社のサステナビリティを実現する5つのポイント
10年後の社会課題に対して貢献価値を発揮するためのポイントを5点まとめます。
1. イマジネーション ~未来の社会像に対する豊かな想像力~
将来を予測することは難しいです。しかし顕在化している未来はあります。例えば、2025年には団塊世代が75歳以上の後期高齢者に到達、また後継者不在企業の廃業急増や既存システムの老朽化などが社会問題とされています。
2027年にはインドのGDPが日本を上回る見込みで、2032年には生産年齢人口が7千万人割り込む見込みです。
2035年にはガソリン車の国内新車販売が禁止され、2040年には医療・福祉分野で96万人の人手が不足する(厚労省推計)といわれています。
このように顕在化している未来を正しく認識し、自社におけるリスクとチャンスを見極めることから始めなければいけません。
自社は関係ないと目を背けていてはリスクへの対応もチャンスを手にすることも手遅れとなります。
2.ビジョン ~共感を生むビッグビジョンの構想力~
日本人は実現可能性を重視し大きなビジョンを立てる(発信する)ことが不得手だといわれます。皆さんが立てられているビジョンはステークホルダーがワクワクするものになっていますか?ビジョンを実現した時のステークホルダーのメリットがしっかり伝わっていますか?
ともに目指したい、実現したいと思える大きなビジョンを掲げられるかが重要です。また実現した時のイメージをビジュアルで示すことも重要です。ムービーにして発信している企業も多くあります。ステークホルダーに共感が得られるビッグビジョンでワクワクする一体感を作り出しましょう。
3.コネクション ~ステークホルダーを巻き込む連携力~
自社だけでやり切るためにすべての機能を保有するというのは今求められているスピード感から考えて少し違うと感じます。餅は餅屋、ビジョンを同じくする仲間と連携して大きな挑戦にスピード感をもって取り組むべきです。自社のビジョンを実現するためにはバリューチェーンのどの部分を強化すべきか、それをステークホルダーとの連携で実現するには具体的にどことどのような連携をするべきかしっかり考えましょう。
地元の自治体との連携を進めておられる企業もあります。供給元との連携や販売先との連携、エンドユーザーとの連携、コンペチターとの連携など今後のサステナビリティを考えると連携は不可欠です。
4.アクション ~社会性と経済性の両立を実現する実行力~
社会性への取り組みか?経済性への取り組みか?という考え方ではなくそのどちらも実現する考え方のもと具体的な行動が重要となります。
"どちらか"ではなく"どちらも"という考え方です。
社会性への取り組みは費用が掛かり経済効率が低下する。一時的にはそのようなこともあり得るでしょう。しかし5年10年先を見据えたときにも果たしてその結果は同じでしょうか?将来の成長に向けた投資とはならないでしょうか?
社会課題解決への取り組みが新たなビジネスや人を呼び込むことにつながります。
中長期の視点でロードマップを描き、足元1年間のアクションプランを具体的に実行していく、この望遠鏡と顕微鏡の視点が今改めて重要となります。
5.コミュニケーション ~早く正しくわかりやすい発信力~
社会課題解決のための取り組みをどれだけの方に発信できているか見直してください。統合報告書やサステナビリティレポートなど多くのレポートが存在します。こういったレポーティングの技術を高めることは企業価値向上のために最も重要といっても過言ではありません。良いビジョンや良いアクションがあってもステークホルダーへ伝わらないということではもったいないです。しっかりわかりやすくタイムリーに発信するとビジネスと人と金が集まってきます。発信しないビジョンは実現せず、伝わらない善い行いは認められないのです。レポーティングの方法は様々あります。組み合わせ方も様々あります。ステークホルダーへ伝わる情報発信に今すぐ取り組みましょう。
企業がサステナビリティ経営に取り組むにあたり事業で社会課題を解決することが非常に重要だと考えます。この事業には本業も新規事業も含まれます。
「サステナビリティ・トランスフォーメーション」というものがあります。SXと表記されます。
これは、5年・10年という長期の時間軸で企業と社会のサステナビリティを同期化させた経営戦略の立案とその実行が必要だという考え方です。企業のサステナビリティとは社会に貢献する事業の稼ぐ力を中長期で持続化・強化することです。社会のサステナビリティとは社会の要請いわゆる社会課題を事業戦略・経営戦略に取り入れることで課題が解決されることです。これが良い循環として螺旋的につながっていく関係性を構築しようというものです。ポイントは5年・10年という長期の時間軸という点です。企業と社会のサステナビリティの同期を実現するためにはやはり時間がかかります。5年・10年で取り組むんだという意思決定がまずは必要です。これはトップマネジメントの役割だと考えます。トップが本気で5年・10年かけてサステナビリティに取り組むという意思を明確に示すことが出発点になります。
企業にとって今後最も重要な戦略の一つが「社会課題解決の事業化」です。本業であっても新規事業であっても社会課題貢献要素を中心に据えることが企業成長のカギです。
社会課題を解決する事業活動が企業価値を向上させ企業と社会の持続的成長につながります。
今一度サステナビリティ経営への取り組み方を見直し、社会課題解決の事業化に取り組んでください。

著者
最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト