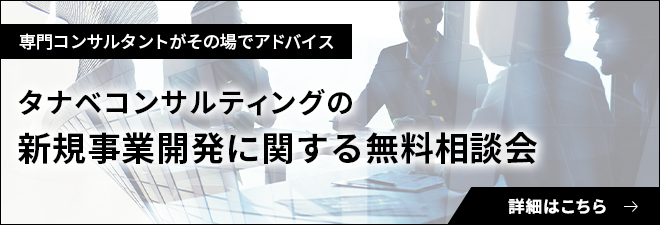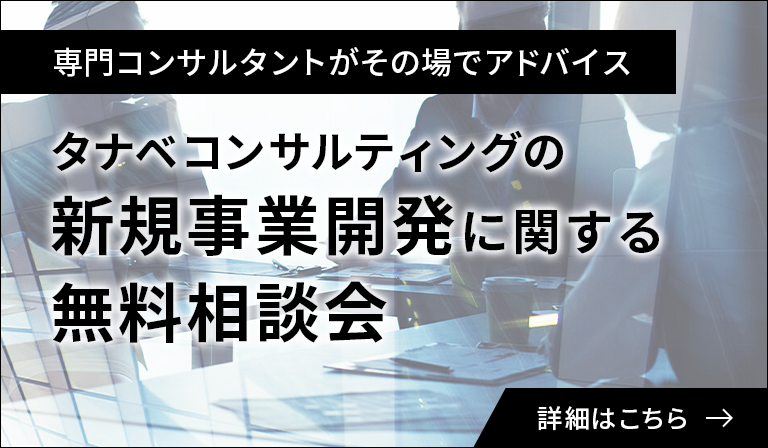CASE
事例
A社 食品製造業
コロナ禍を契機に、
新事業へ挑戦するための中期経営計画を策定
新型コロナウイルス感染症の流行により、業績に大きな影響を受けていた食品原料販売を主たる事業とするA社からの相談を受け、ウィズコロナ、その他食品市場の変化を見据えた新しい経営ビジョンを中期経営計画(5ヵ年)として策定しました。
クライアント企業(A社)の概要と課題
国内食品メーカーへの原料販売事業および食品製造受託販売事業
新型コロナウィルスによる業績不振、それを補う新規事業の不足
A社は本社を大阪に置く、海外原料を国内食品メーカーに販売することを中心事業としている会社です。30年以上続く会社で、上記中心事業以外にもこれまで食品製造受託販売事業や粉末原料を混ぜ合わせて自社製剤を製造販売する事業を展開してきました。社員は約120名で少数精鋭で高品質・高機能の商品を乳業メーカー、総菜メーカー、製パンメーカーなどの様々な食品メーカーに販売してきました。
2020年当時、食品市場は植物肉、SDGs、クリーンラベルニーズなど大きな市場変革が起こりつつある状況でした。そして、新型コロナウィルスの流行により、当企業においても例外なく業績に大きな影響があり、単に食品メーカーに原料を販売するビジネスモデルだけでは今後急速に市場が変化した場合に対応できないことが企業としての課題でした。そこでこの課題を解決するために、新型コロナウィルスの流行という逆境を跳ね除けるだけでなく、今後の新しい企業価値の創出のために新規市場への参入、新しいビジネスモデルの構築を行うための中長期での経営ビジョン及び事業計画を策定する必要がありました。
コンサルタントならではの複眼の客観的論理的な現状分析
現状の認識と戦略の軸とすべき強みの再発見
まずはA社の役員、各部署長、担当者へのヒアリング、A社蓄積データ分析により内部現状を把握し、さらにA社を取り巻く外部環境を分析を加えて、改善していくべき点や今後の成長の軸にすべき点を検討しました。現状認識におけるポイントは、上記課題を踏まえると、既存事業での改善すべき点の洗い出し、かかる改善を含めた上で既存事業へどのくらい費用と工数をかけていくべきか、新規事業へどのくらい費用と工数をかけられるのか、という点でした。また、新規事業を展開する上でどのような市場への参入が可能なのか、競合他社はどういったビジネスモデルで事業展開しているのかを検討しながら、A社は何を強みとして事業を展開していけるのか、がポイントでした。
現状認識に基づく計画策定の方向性
客観的視点且つ総合的な経営計画の策定
上記現状分析結果を踏まえて、中期経営計画策定の際のポイントをとして以下の点が挙げられました。
まず、予測困難な市場変化の中で新規事業、新たなビジネスモデルを計画する上で、従来のやり方に捉われず市場をより広い視点で捉えることが必要でした。A社には原料を使用した加工食品の高い設計技術があり、それを活用することで従来の粉末原料の販売だけにとどまらず、原料を加工した加工食品などを販売していける可能性がありました。
また、新規事業を展開するにしても、資源がないことには継続していくことができないので、基盤事業をより盤石にすることが重要であると捉え、業務効率を考えた組織体制やDXを組み込んだ営業システム、管理システムを構築することにしました。
そして、事業内容のテコ入れもさる事ながら、基盤事業に資源を割きながら新規事業を積極的に展開していくのであれば、かかる観点で費用の配賦、投資、人事組織といった経営体制についても見直しを図る必要がありました。
上記3点を踏まえると、会社の一部機能の改善だけではなく、会社全体の各機能を総合的に見直しながら、中長期の経営ビジョンと事業計画を客観的かつ総合的に作成していくことが求められていたといえます。
A社の固定概念を打破した革新的な中期経営計画の策定
半年間で新たな企業価値を創出するための実行計画が完成
上記計画策定の方向性を摺合わせ、A社課長職以上の社員を中心として、計画策定を実施しました。策定にあたっては管理・財務、事業、人事組織、DXの部門毎に分かれ、担当者を含めて協議を重ねていきました。具体的な現場担当者を含めて、協議する領域を意図的に限定することで、より具体的なアイデアや実現性のあるアクションプランを策定することができました。以下にA社中期経営計画のポイントを挙げます。
1. 経営ビジョンについて
これまでのA社からの「変革」、食品市場自体の「変革」をキーワードに、これまでの固定観念を脱却した企業としての変革を目指した経営ビジョンを構築できました。また、かかるビジョン実現のためにA社の強みである組織間の相互協力体制を元に、それぞれの社員がアイデアを考え、その実現に向けてチャレンジできる風土を形成するためのバリューを策定しました。
2. 組織体制について
少数人員で新たに事業創出を行う必要があるため、組織の枠に捉われないで新規事業創出の取り組みを推進する組織横断型のユニットを発生させる仕組みを構築しました。この制度を導入することにより、優先度の高い案件を必要な能力のある社員を集めて、より的確にスピーディーに進めることができるような体制を作ることができました。このユニットはA社には従来から組織間で協力し合う体制があったという会社風土としての強みを活かしたものです。企業としての強みを新規事業の開拓に活かす積極的な組織を作ることができました。
3. 既存事業活動の効率化
少数人員で効率的に営業活動ができるようなマーケティングオートメーション、マーケティングに基づく商品開発フローの構築、社内管理システムの連結などDXによる各種社内インフラの再構築を計画しました。やはり限られた資源の中で、既存事業を強化しながら新規事業にも着手していくためには、効率的な業務体制や効率的な営業活動を構築することが重要でした。そのため社内システムや営業システムにDXを積極的に取り入れ、より効率的に既存事業を強化、拡大させていくためのDXによる社内インフラ整備を計画しました。
4. 事業戦略について
新規事業として、これまでの原料の販売におけるプロセスで培った原料の加工技術を活用して、加工食品の販売への商品カテゴリの拡大に着手することを計画しました。また食品製造受託販売で培った食品設計技術を活用して、製造納品までの一貫したプロセスだけでなく、食品設計から製造までの各プロセスをサービスとして提供するODM事業の本格稼働を計画しました。さらにはかかる食品設計技術を活用してECチャネルに対して直接食品を販売していくビジネスモデルにも挑戦することを決めました。
5. 計画進捗管理について
策定した計画の実現のために、達成度を数字で評価し更新していくことが必要でありました。そこでKGI・KPIマネジメントの仕組みを導入して、現場での計画進捗を数字で管理するできるような体制を構築しました。また、経営状況も数字で管理し、数字に基づいた経営戦略を常に検討できるように管理会計の導入も併せて実施しました。
このように、従来のビジネスモデルから新たなビジネスモデルへの挑戦を会社全体の仕組みを総合的に見直して、A社の強みを活かした多角的な事業展開によりこれから先の市場の変化に対して柔軟に対応していくためのビジョンと計画を策定することができたといえます。
会社プロフィール
A社 食品製造業
[ 所在地 ]
大阪府
| 所在地 | 大阪府 |
|---|---|
| 売上高 | 50億円 |
| 従業員数 | 約120名 |
最新事例

- 長期ビジョン・中期経営計画策定による事業拡大
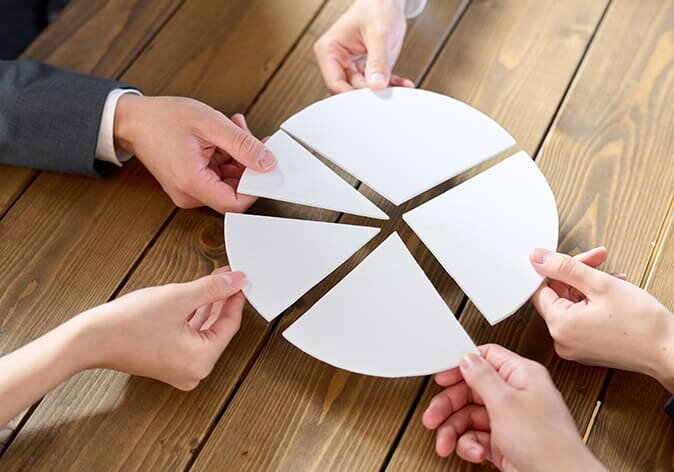
- 建設業における働き方改革と業務効率化の実現:工務部の設立と現場との役割分担による成功事例

- 設備工事業における業務見える化取り組み事例

- 中長期ビジョンの再デザインのための事業ポートフォリオ変革
コンサルタント紹介

- タナベコンサルティング
取締役
ストラテジー&ドメインコンサルティング事業部山本 剛史

- タナベコンサルティング
取締役
ストラテジー&ドメインコンサルティング事業部村上 幸一

- タナベコンサルティング
上席執行役員
九州本部高島 健二

- タナベコンサルティング
上席執行役員
ストラテジー&ドメインコンサルティング事業部土井 大輔
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト