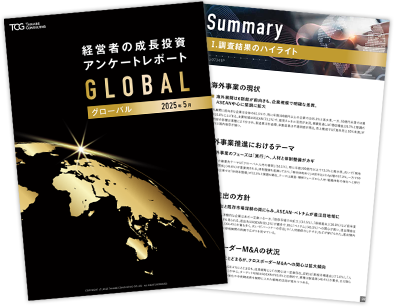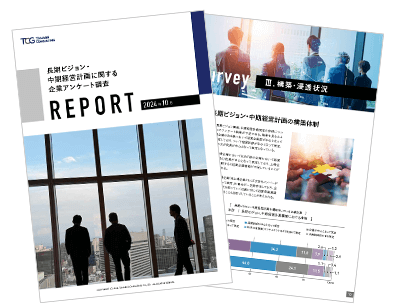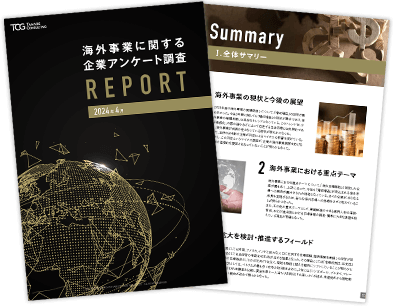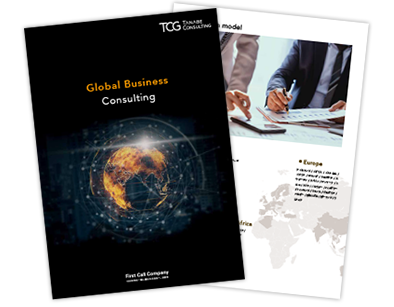COLUMN
コラム
閉じる

インドネシアは、ASEAN最大の経済規模を誇り、人口約2億8,000万人を抱える巨大市場です。政府は、建国100周年を迎える2045年までの先進国入りを掲げ、世界の注目を集める次期経済大国として大きな存在感を示しています。しかし、魅力的な市場である一方、周辺のASEAN主要各国と比較すると、外国企業にとっては参入が難しい国の一つと言われています。参入障壁が高いことは競合企業にとっても同様ですので、しっかりとその壁の構造を把握し、適切な越え方やかわし方を理解することが、同国への進出を成功へと導くカギとなります。本コラムでは、インドネシア市場の魅力と障壁のギャップから、インドネシアへの進出検討において重要となるポイントを解説します。
インドネシア市場概況と進出が注目される理由
(1)広大な国土と巨大な人口
インドネシアは、赤道直下に位置し、南北約2,000㎞、東西約5,000㎞と日本の約5倍の国土に約18,000以上の島々が広がる広大な島嶼国です。2024年の中央統計庁統計では約2億8,000万人と、アメリカに次ぐ世界第4位の人口を有し、その平均年齢は約30歳と若く、人口ボーナスは2040年頃まで継続すると予測されています。政治・経済の中心であるジャカルタは人口約1,070万人を抱え、ASEAN最大のメガシティを形成しています。ジャカルタに隣接する1州・4県・4都市から成るジャカルタ都市圏は約7,600㎢の面積に3,200万人以上(マレーシア総人口の約95%に及ぶ)人口が暮らし、東京都市圏、デリー都市圏に次ぐ世界第3位の都市圏人口規模を誇ります。
(2)外需依存の低い強固な経済成長基盤
インドネシアは、石油・天然ガス・石炭・鉱物等の豊富な天然資源を有する国です。主要産業は、製造業、農業、サービス業であり、特に製造業は、日本をはじめとする多くの外国企業も生産拠点を構え、同国の経済成長における原動力となっています。また、従来から外需に依存しない内需主導型の経済構造であり、巨大な人口、増加する中間所得層とその購買力が、今後5年間も平均5%台と高い経済成長率が維持されていくとの予測を裏付けています。2023年時点でのGDPは約1兆2,000億米ドルに達し、世界16位、ASEAN諸国の中では最大の経済規模を誇ります。2050年には中国、アメリカ、インドに次ぐ世界第4位に達し、日本を上回る経済規模となることが予測されています。
(3)世界有数のEコマース市場
インドネシア政府は、経済成長促進を目的としたインフラ整備・投資環境改善に加え、デジタル経済の発展にも注力しています。2024年1月時点のインターネット普及率はインドネシア国内で79.5%、ジャカルタでは87.5%であり(出典:APJII-インドネシア・インターネット・プロバイダー協会)、日本全国の86.2%(出典:総務省「通信利用動向調査」2023年8月末時点)を超える水準となっています。同国Eコマース市場全体の売上は約970億米ドルと、インドに次ぐ世界第7位の規模であり、ASEANのEコマース市場全体の約半数を占め、ASEAN地域ダントツの売上規模を誇ります。豊富な人口に加え、その若年層や中間所得層の増加が、ASEAN最大の消費市場を形成し、デジタルマーケティングやEコマース分野でのビジネスチャンスが急速に拡大しています。
(4)急増する中間所得層と都市部の購買力
2000年頃には僅か30%ほどであった中間所得層の割合は、2023年時点で72%(2億人)を超えるまでに急増しています。2045年の高所得国(先進国)入りを目指す政府は、同年までに中間所得層の割合を国民全体の80%以上とすることを掲げています。一人当たり名目GDPの観点では、3億に迫る巨大な人口を抱えているため、僅かUSD4,942/人(約70万円)と日本の約1/7ほどの水準に留まる一方、ジャカルタでは、USD21,173/人(約300万円)と日本とそん色のない水準に迫っています。この一人当たりGDPの水準は、ASEAN諸国において、シンガポール、ブルネイに次ぐ第3位となり、マレーシアを上回ります。つまり、インドネシア全土で見るのか、ジャカルタ都市部で見るのかによって、同国市場を攻略するための戦略設計も大きく異なるということが理解できるでしょう。

インドネシア進出における課題と対策
前述の通り、インドネシアは非常に魅力的な成長市場である一方、進出には高いハードルがあることも事実ですが、事前にしっかりと理解し、適切な対策を講じることで克服することが可能です。
(1)法規制の複雑さ
インドネシアの法規制は、周辺のASEAN主要各国と比較しても複雑で、且つ頻繁に改訂されることでも有名です。政府は国外からの投資誘致に積極的である一方、内資企業保護の観点から、未だ外国企業に対する厳しい規制が敷かれています。外資法人の設立に際しては、約9,500万円の最低振込資本金が求められ、事業ライセンスも非常に細かく分類されています。また同様の観点から、世界で最も輸入規制が複雑な国の一つとも言われており、情報収集が困難な国の一つです。従って、デスクトップで収集できる主な規制情報(建前)だけではなく、実態を熟知する現地法務専門家のアドバイスを受け、コンプライアンスを徹底することが必要となります。インドネシアに限られた話ではありませんが、同国進出に対するリスクマネジメントにおいて、特に重要なプロセスとなりますので、必要投資として計画策定の段階から検討しておくことを推奨します。
(2)文化・商習慣の違い
海外進出・展開において一般的な観点ではありますが、その中でもインドネシアは多様な文化を持つ多民族国家であり、文化的違いの理解度がビジネスに大きな影響を与えることがあります。現地の文化・商習慣を十分に理解(尊重)し、柔軟な対応を心掛けることが重要です。特に、コンプライアンス意識の違いには十分に注意する必要があります。同国では大臣クラスの汚職・賄賂が社会問題となっており、世界各国の腐敗や汚職を監視する国際的なNGO「トランスペアレンシー・インターナショナル」の発表によると、世界腐敗認識指数ランキング115位(2023年時点)で、ASEAN主要国の中で最低の水準となっています。進出にあたり、自社が関係各所からそうした便宜供与を求められるリスクに限らず、進出後に現地拠点社員が内部不正に手を染める隙を作らないガバナンス管理の視点が非常に重要となります。
(3)競争の激化
魅力的な成長市場であるが故に、進出後の市場競争も日々激化しています。JETROの海外進出日系企業調査(2024年度)によると、特に現地企業のコスト競争力の高さと、意思決定スピードの速さを脅威と捉えている日系企業が最も多いことが理解できます。一方、政府は親中として知られる同国ですが、競争相手として、現地企業の次には日本企業が挙がり、中国企業は3番目に位置しています。製造業に絞った回答結果を確認しても、他のASEAN主要国と比較し、中国企業を競争力が強い相手に挙げる日本企業の数は少ない傾向が見て取れます。近年の直接投資額では中国が存在感を示していますが、民間レベルでは、未だ"Japan Quality"のプレゼンスが高い世界最大の親日国です。綿密な競合分析から自社のポジショニングをしっかりと理解した上で、現地企業との価格競争を避け、差別化された製品やサービスを提供し、付加価値による競争力を高めるブランディング戦略の設計も重要なポイントとなります。
(4)物流インフラの脆弱性
広大な国土を有する島国であるインドネシアは、その地理的要因から、大都市圏以外の地域におけるインフラが未整備である現実もあり、物流に課題が生じることがあります。日本も同じ島国ですが、インドネシアにおいて日本同様の陸運物流をイメージすることは危険です。特にコールドサプライチェーンは未だ発展途上にあり、温度管理が必要となる食品や医薬品の物流には注意が必要となります。前章で述べた通り、ジャカルタか、それ以外かという観点に基づき、事前調査を実施した上で、進出初期フェーズの事業展開エリアを慎重に選定することが重要となります。

進出前の準備と考慮すべきポイント
前述の課題と対策を踏まえ、以下の通り、インドネシア進出の成功確率を高めるための事前準備事項と考慮すべきポイントを解説します。
(1)綿密な市場調査・分析
インドネシアは進出後に「こんなはずではなかった...」と理想と現実のギャップに嘆く外国企業が多い国の一つです。また、他のASEAN主要国と比較し進出における初期投資額が高くなる傾向もあり、このギャップは大きな経営インパクトを与えるリスクとなります。法規制の理解のみでリスク回避にはなりません。現地市場ニーズ、競争環境や商習慣を事前に把握しておくために、徹底的な市場調査を行うことが重要です。これにより、ターゲット市場を明確にし、競争力の高いビジネスモデルを設計し、実現可能性の高い戦略を立てることが可能となります。また、特に新興国での事業展開に不慣れな場合は、専門家による助言を仰ぐことを強くおすすめします。
(2)現地パートナーの選定
外国企業にとって制約の多い市場であるため、現地ビジネス環境や商習慣に精通したパートナーを選定することで、進出プロセスを円滑に進めることができるだけでなく、進出後の成功確率を高めることに直結します。パートナー企業の選定に当たっては、候補企業との対話を通じた事前の信頼関係の構築が非常に重要となります。デスクトップにて収集可能な企業情報は非常に限定的であるため、候補企業のリストアップや初期接点の創出においては、専門家や現地業界関係者のサポートを受けることを推奨します。候補企業との折衝においては、可能な限り社長や経営陣が自ら足を運び、五感で現地を体感することがポイントとなります。現地大手企業であっても、公表されている財務情報と実態が異なるケースも散見されますので、経営トップ同士の対話による体感という曖昧で感覚的な情報も、意思決定に必要な要素となることにも理解が必要です。その上で、企業調査でも払拭できないパートナー企業の経営リスクに関しては、契約の諸条件にて担保することが重要となります。また、M&A等の資本関係を持たないパートナーシップを構築する場合は特に、一方通行の片思いにならないことが重要です。パートナー企業との相互シナジーが発揮できることが最重要であり、両想いの関係性ができて初めて事業成長に繋がることを意識する必要があります。
(3)宗教・文化的適応
インドネシアは多様な宗教・文化を持つ世界有数の多民族国家であり、そのニーズに適応した商品・販売戦略が求められます。特に、食品や化粧品などの日用品や消費財においては、人口の80%以上を占めるイスラム教徒の消費者インサイトに配慮する必要があります。自社でのハラル認証取得、もしくはハラル対応工場を持つ現地製造パートナーとの提携等、市場調査を踏まえ、進出計画段階から、ハラル対応における手段別の費用対効果や投資判断基準も合わせて検討しておく必要があります。一方、インドネシアで戦うにはハラル対応が必須であると、一概には言えません。人口の僅か数パーセントである富裕層の殆どを中華系が占めているため、この層をターゲットとした高級商材の場合はイスラム教を強く意識する必要がなくなります。人口の僅か数パーセントであっても、数百万人規模の富裕層市場と考えると、シンガポールと同等以上の市場が存在していると言っても過言ではありません。いずれにしても、このようなマーケット環境や現地消費者ニーズを十分に把握するための市場調査が前提とした、実現可能性の高い商品・販売戦略の構築が必要となります。

まとめ
弊社に寄せられるASEANへの進出や展開のご相談の中でも、対象国として最も件数が多いのがインドネシアです。その理由としては、市場の魅力度と進出・参入難易度の大きなギャップにあると考えています。同国への進出や市場参入によって、日本国内市場では難しい大きな持続的成長を描けるというメリットがありますが、入念な事前準備と実現可能性の高い戦略を持たずして、その達成は見込めません。むしろ、事前準備(成長投資)を疎かにしたインドネシア進出は日本企業にとって大きなリスクとなり、参入自体がデメリットとなります。進出や参入難易度が高いことを理由に、ASEANへの進出や拡大検討の初期段階でインドネシアを仮想ターゲット市場から外してしまうこともまた、大きなチャンスを放棄してしまうことになります。単純に「投資・参入ハードルが低ければ良い」という「進出することがゴール」という思考に陥らず、進出後の現地マーケットで事業を成功させることを念頭に置いた計画(市場攻略に向けた戦略)が必要不可欠です。綿密な事前調査・分析、相互シナジー発揮が可能な現地企業とのパートナーシップの活用検討や、商習慣・宗教・文化的な購買意思決定要因の違いに適応することで、十分な競争力と収益性を確保することが可能な市場です。他社のインドネシア進出・投資動向等に一喜一憂せず、自社が同国市場で成功するための要素を冷静に整理する「急がば回れ」の戦略策定が、持続的成長を実現するための近道となります。
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト