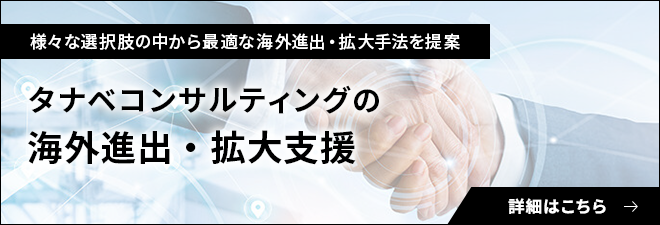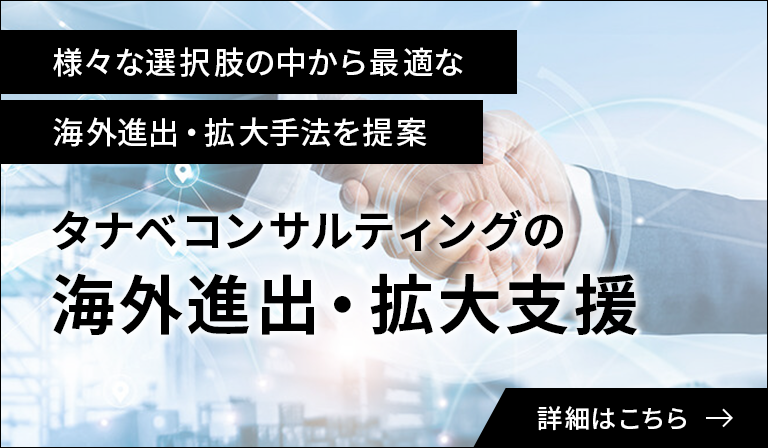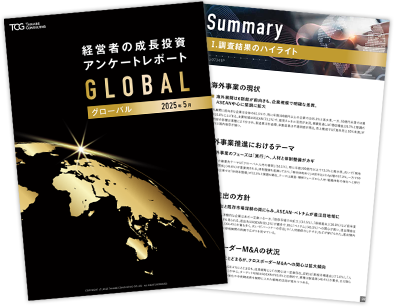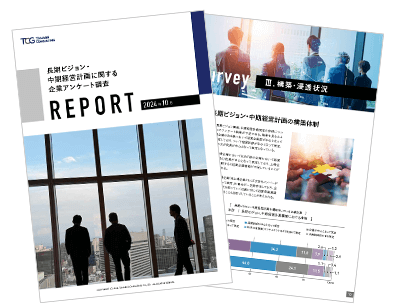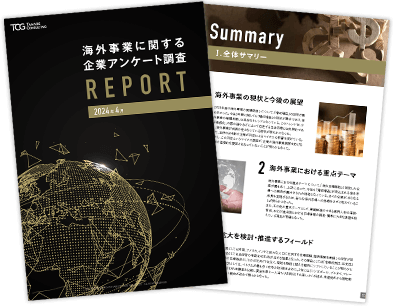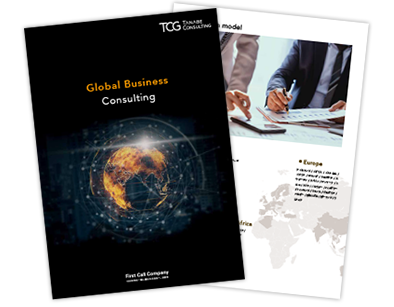COLUMN
コラム
閉じる

東南アジアM&A市場の現状
(1)成長市場としての魅力
東南アジアがM&A市場として注目される最大の理由は、その市場としての成長性にあります。ASEAN10カ国の総人口は約6.7億人に達し、その約半数が30歳以下の若年層です。また、中間所得層の拡大により消費市場としての魅力も高まっており、2030年までに中間所得層人口は現在の2倍以上に増加すると予測されています。
さらに、デジタル化の進展も著しく、特にインドネシア、ベトナム、タイなどでは、Eコマースやフィンテックなどのデジタル産業が急成長しています。このような背景から、製造業に限らず、小売、サービス、テクノロジーなど幅広い分野での投資機会が生まれています。
(2)M&A投資の動向
近年、日本企業は東南アジア市場における競争力を高めるため、製造業や食品業界において積極的な買収活動を展開しています。

日本企業による主要な買収事例
(1)マルハニチロのベトナム進出
マルハニチロは2021年にベトナムの水産加工品製造会社であるサイゴンフードを買収しました。この買収により、マルハニチロは日本向けの水産加工品の供給体制を強化するとともに、ベトナムを拠点にした生産基盤を確保しました。東南アジアは水産資源が豊富であり、サイゴンフードの製造能力を活用することで、マルハニチロは価格競争力を高め、さらに多様化する消費者ニーズに応える製品開発を加速させることができます。
(2)キリンホールディングスのミャンマー進出と撤退
キリンホールディングスは、2015年8月19日にミャンマー最大のビールメーカー、ミャンマー・ブルワリー(MBL)の株式55%を5億6000万ドル(約697億円)で取得し、ミャンマー市場に本格参入しました。この買収は、国内のビール市場が縮小する中、成長が見込まれる新興国での事業強化を目的としていました。
MBLは「ミャンマー・ビール」、「アンダマン・ゴールド」などのブランドを持ち、ミャンマーで約80%のシェアを有していました。当時、ミャンマーのビール市場は21万キロリットル(キリン推定)で、一人当たりのビール消費量は低水準でしたが、将来的に大きな成長が見込まれていました。
キリンホールディングスは、MBLにキリンの技術・ノウハウを加え、一層の成長を図る計画でした。また、ミャンマー国軍系企業のミャンマー・エコノミック・ホールディングス(MEHL)が残りの45%の株式を保有し、現地企業と組むことのメリットを活かす戦略を取りました。
しかし、2021年2月のミャンマー軍事クーデター後、キリンホールディングスは国軍系企業との合弁解消を要求し、2022年2月に保有する全ての株式を6月末までに売却する方針を明らかにしました。
キリンホールディングスは欧米企業を含め売却先を探しましたが、人権弾圧を続けるミャンマー国軍への国際的な批判が強まる中、国軍系企業以外の有望な買い手は現れませんでした。最終的に、2022年6月30日、キリンホールディングスはMBLの全保有株式をMBLに約224億円で売却することを決定しました。
この撤退により、キリンホールディングスは投資額の約3分の1(約230億円)について回収のめどが立たなくなりました。また、2022年12月期にその他営業収益として190億円を計上する一方、株式譲渡時にはその他営業費用として180億円を計上する見込みとなりました。
キリンホールディングスは2023年1月23日に、MBLの全保有株式をMBLに売却したと発表し、ミャンマーからの撤退を完了しました。
この事例は、東南アジア市場への進出の機会と同時に、政治的リスクや人権問題などの課題も示しています。日本企業が海外M&Aを行う際には、市場の成長性だけでなく、政治的・社会的リスクも十分に考慮する必要があることを教訓として残しました。
(3)イオングループのマレーシア展開
イオングループは、1984年にマレーシアに進出し、2012年にカルフール社のマレーシア事業を約151億円で買収しました。この買収により、イオングループは一気に同国第2位の流通企業グループへと躍進しました。
イオングループの成功の鍵は、現地消費者のニーズを徹底的に理解し、日本式のサービスを現地文化に適応させたことにあります。マレーシアの多民族・多宗教社会の特性を考慮し、ハラル認証商品の充実やローカルブランドの積極的な導入など、きめ細かな戦略を展開しました。
また、イオングループはショッピングモールの開発にも注力し、単なる小売店舗ではなく、エンターテインメントや飲食、サービス機能を備えた複合型商業施設として展開しました。これにより、マレーシアの消費者のライフスタイルに合わせた新しい購買体験を提供することに成功しました。
現在、イオングループはマレーシアで「イオンモール」を28店、総合スーパー(GMS)を35店、食品スーパー「マックスバリュ」を7店運営(そのほか、イオンマレーシアの事業会社が、仏カルフールから買収した店舗を転換したディスカウントストア(DS)「イオンビッグ」も21店営業する)するまでに成長しています。この成功は、長期的な視点での投資と、現地市場への深い理解、そして柔軟な事業戦略の結果といえるでしょう。
(4)ユニ・チャームのベトナム展開
ユニ・チャームは2011年、ベトナムの衛生用品メーカーであるダイアナ社を買収し、現地市場での基盤を確立しました。この買収は、急速に成長するベトナム市場でのシェア拡大を目指したものでした。
ユニ・チャームは、ダイアナ社の現地ブランドと販売網を活用しつつ、日本の高度な技術を導入することで、製品の品質向上と多様化を図りました。特にベビーケア事業に注力し、2014年には主要2都市で40%以上のシェアを獲得するまでに成長しました。
成功の要因として、ユニ・チャームはエコノミーからプレミアムまでの多様な製品ラインナップを展開し、ベトナムの消費者の多様なニーズに応えたことが挙げられます。また、現地の文化や習慣に合わせた製品開発や、きめ細かなマーケティング戦略も功を奏しました。
さらに、ユニ・チャームは生産拠点の現地化も進め、コスト競争力を高めると同時に、現地雇用の創出にも貢献しました。これにより、ベトナム政府からの信頼も獲得し、事業拡大の基盤を強化することができました。
ユニ・チャームのベトナム展開は、M&Aを通じた市場参入と、その後の現地化戦略の成功例として、多くの日本企業に示唆を与えています。

東南アジアのM&A成功のポイント
(1)現地市場と文化の深い理解
表面的な市場データだけでなく、消費者の嗜好や商習慣、ビジネス文化などを十分に理解することが求められます。
(2)適切なバリュエーションと徹底したデューデリジェンス
東南アジアの企業は、財務情報の透明性や企業統治の面で課題を抱えていることも少なくありません。そのため、買収前の詳細な調査と適切な価格設定が成功の鍵となります。
(3)ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)の重要性
買収後の統合プロセスでは、現地の経営陣との信頼関係構築や、従業員のモチベーション維持が極めて重要となります。

結論:戦略的アプローチの重要性
東南アジアでのM&Aは、日本企業にとって重要な成長戦略の一つとなっています。その成功のためには、単なる市場参入や規模の拡大を超えた、戦略的なアプローチが不可欠です。現地の特性を理解し、長期的な視点で取り組むことで、持続的な価値創造が可能となるでしょう。
本稿で紹介した東南アジアのM&A成功事例とポイントが、今後東南アジアでのM&Aを検討する企業にとって、有益な示唆となることを期待しています。
著者
最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- デスクトップリサーチを用いた海外市場調査の具体的な方法を紹介!
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト