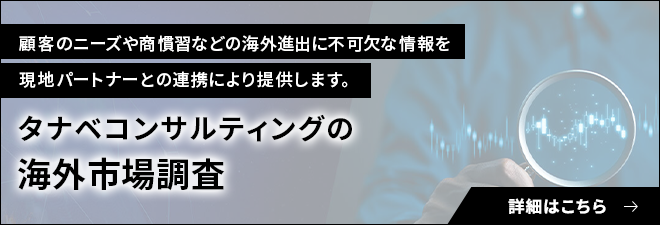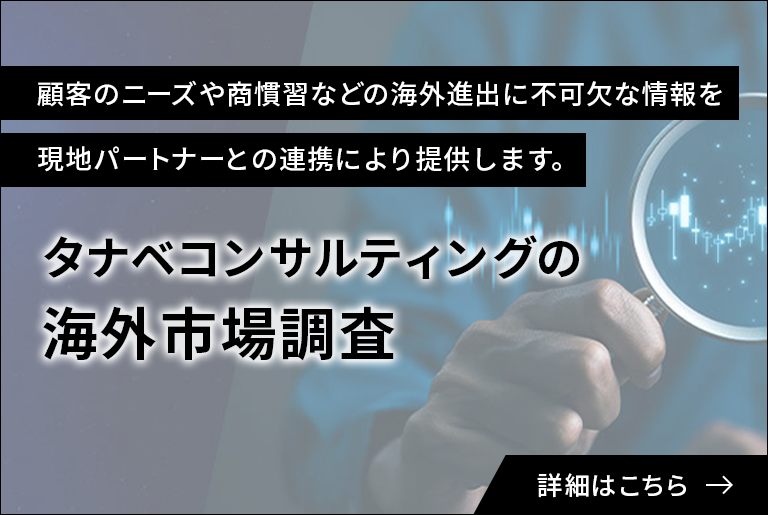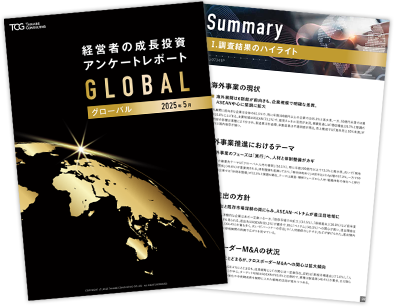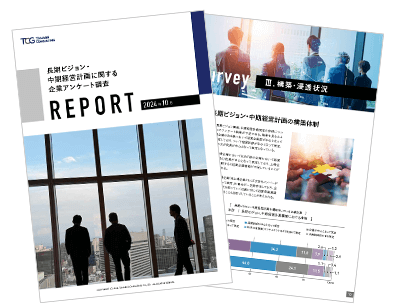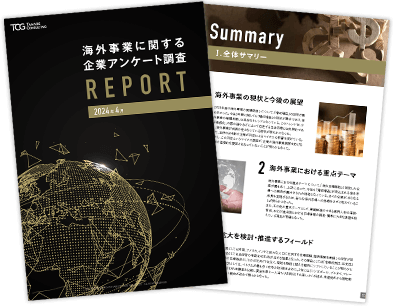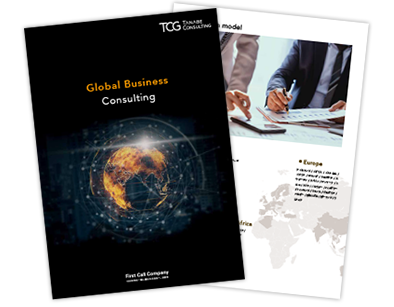COLUMN
コラム
閉じる

本コラムでは、日系中堅・中小企業のASEAN進出や現地子会社管理の失敗事例を基に、海外展開を失敗させないためのポイントを解説します。
海外事業展開の重要性
少子高齢化の加速による日本国内の内需縮小、グローバリズムの進展、ダイバーシティー&インクルージョンという価値観の浸透などを背景に、日本企業がグローバル化に挑む必然性は一段と高まり続けています。
あらゆるものが統一化・標準化されていく世界において、海外展開は非常にオーソドックスな成長戦略の一つといえます。
現在の世界各国のスタートアップ企業の中には、最初から自国だけでなく世界をターゲットとして創業している"ボーン・グローバル企業"が数多く存在し、自社が海外に進出しなくても、グローバル競争の渦中に飲み込まれていく時代になっています。
したがって、日本企業が持続的に成長を遂げるためには、グローバル戦略の構築が不可欠です。
グローバル・ビジョンをアップデートし、それに基づく長期視点の戦略をデザインすることが、日本企業の成長を左右する重要な鍵となります。
弊社が2025年3月に実施した「経営者の成長投資アンケート(グローバル)」によると、海外事業に既に取組んでいる、あるいは今後取組む意向を持つ企業は全体の6割を超えており、一定の広がりを見せています。
実際に「展開している」と回答した企業は43.2%、「現在は展開していないが今後取組みを検討中」と回答した企業は18.3%であり、海外展開に前向きな姿勢がうかがえる結果となりました。
また、ジェトロが2024年8月から9月にかけて実施した「海外進出日系企業実態調査」によると、営業利益が黒字と見込む企業の割合は65.9%と2年ぶりに増加傾向となっています。
インド、ブラジル、メキシコ、ベトナム、インドネシアなどのグローバルサウス主要国では旺盛な内需が業績改善を後押ししており、市場環境の好転が追い風となっています。
こうしたチャンスを的確に捉え、自治体や政府の補助を活用しながら、積極的に海外事業展開を進める中堅・中小企業が増加しているのも現状です。
※出典1:経営者の成長投資アンケートレポート GLOBAL(株式会社タナベコンサルティング)

「とりあえず海外!」のリスク
一方、海外展開が当たり前となってきている環境下では、自社の取組みの遅れに焦りを感じる経営者の声も多く聞かれます。
「知人の紹介で海外進出の良い話をもらい、輸出販売を検討している」や「現地企業で有望な売り案件があり、買収を検討している」など、周囲の海外進出を横目に"良い話"へ期待を寄せる経営者の方々とお話しする機会が増えています。
このように、目の前のチャンスをつかみ海外展開を成功させている企業もありますが、同時に「とりあえず海外へ」と動き出したことで失敗に至ったケースも少なくありません。
以下では、海外進出自体が目的となり、結果として失敗した日系中堅・中小企業の事例を紹介します。
インドネシア×コンシューマープロダクト製造業
3億人に迫る世界第4位の人口を抱え、平均年齢は約30歳と、世界からも注目される巨大な消費市場である同国の潜在性に期待し、コンシューマープロダクトの現地販売会社を設立。
輸入・流通コストを抑えるため現地OEM先への委託製造を進めましたが、原材料の現地調達率の低さや構成部品の輸入規制に対応しきれず業績が悪化しました。
「日本品質」以外の付加価値を打ち出せず、ローカル製品との差別化にも失敗し、再編や撤退を検討せざるを得ない状況に陥りました。
駐在員社長は現状を打破するため、輸入規制に詳しい法務コンサルタントや現地パートナーの開拓に奔走しましたが、本社の理解を得られず頓挫。
既存の現地代理店やOEM先との関係も悪化し、事業継続が困難となりました。
ベトナム×金属加工業
日系企業の進出ラッシュに乗じ、自社の主要事業との親和性が高い日本人経営のローカル企業を買収。
既存顧客への依存度が高かったものの、当初は日系企業の投資が好調で業績も順調に推移しました。
コロナ禍を経ても日系企業による中国から同国への生産移管が続き、業績の回復が期待されましたが、2023年以降もコロナ前の水準を大きく下回り、3期連続赤字見込みとなりました。
海外ノウハウが乏しく、社内に適任者もいなかったことから、買収後も前身企業の経営陣に権限の大半を委譲しており、本社では実態を十分に把握できていませんでした。

失敗のリスクを抑制するためのポイント
インドネシア×コンシューマープロダクト製造業のケース
自社製品への慢心と不十分なマーケット調査
どれだけ自社製品に優位性があっても、日本とは全く異なる嗜好や価値観を持つ消費者がターゲットとなる以上、日本ブランドだけで勝てるほど容易な市場ではありません。
特にインドネシアは世界有数の多宗教・多民族国家であり、日系企業がテストマーケティングや市場調査を行わずにコンシューマープロダクトを展開するのは、極めてリスクの高い判断といえます。
本社依存の意思決定により加速しない事業スピード
当初、駐在員社長は本社の意向を忠実に反映した経営を行っていましたが、現地の実情を十分に踏まえたものではありませんでした。
情報収集や人材採用への投資を避けようとする本社経営陣との間に大きな溝が生まれ、複雑な法規制への対応や優秀な現地人材の採用・定着、ローカル製品との差別化に必要な市場分析などが進まない状況に陥りました。
事業推進や拡大に必要な人・組織・情報といった基盤の盤石さこそが、未知の市場で戦う上での重要な武器となります。
パートナー企業との深まらないコミュニケーション
このような意思決定スピードの遅さは、有望なパートナーとの業務提携の機会損失にもつながります。
カウンターパートが非上場企業である場合、日本のように企業調査や与信調査を行うことは難しいのが実情です。
そのため、あらかじめ協力企業に求めるケイパビリティや条件を定めておくことで、行き当たりばったりの交渉を避け、現地主導でのリスク回避とスピード感ある意思決定が可能になります。
ベトナム×金属加工業のケース
M&A時の不十分な企業調査
近年では、中堅・中小企業においてもクロスボーダーM&Aを通じた海外進出が増えており、資金力のある大企業だけの手段ではなくなりつつあります。
しかし、事前の各種デューデリジェンス(企業調査)や事業性評価が不十分な場合、買収後に思わぬトラブルが発生する可能性があります。
特にローカル企業のM&Aを検討する際には、簿外債務や隠れた負債、財務上の不正などのリスクを内包しているケースも少なくありません。
そのため、そうしたリスクを洗い出し、実態を正確に把握し、冷静に評価することが求められます。
現地への過度な権限移譲(名ばかりのローカライズ)
海外事業の推進人材や駐在員候補の不足は、多くの日系企業が抱える課題です。
一方で、決裁フローや本社を介した管理スキームを整備しないまま、権限の大半を現地経営陣へ実質的に移譲してしまうと、対象子会社の実態把握が困難になり、経営がアンコントロールな状態に陥るリスクがあります。
リアルタイムで業績を把握できるERPや基幹システムの導入、信頼できる現地日系会計事務所への業務委託など、遠隔だからこそ本社がしっかりとガバナンスを効かせる仕組みづくりが重要です。
現法⇔本社の希薄なコミュニケーション
日本人駐在員の派遣が難しく、適切な人材を採用できない場合、現地子会社の経営陣とのコミュニケーションが希薄になりがちです。
本社理念の浸透不足や言語の壁に加え、現地会計基準や税務ルールへのキャッチアップが遅れることで、子会社の財務報告の信頼性を疑わざるを得ない悪循環に陥ります。
それを防ぐためにも、進出初期段階で信頼できる専門家への委託や、管理スキームの整備に注力することが重要です。

まとめ
海外子会社で問題が発生してから体制を再構築するのは、進出初期に整備する場合とは比べものにならないほどの労力とコストがかかります。
結果として、事業継続が困難になるケースも少なくありません。
海外進出のハードルが下がり身近になった今だからこそ、進出をゴールとせず、現地で持続的な成長を実現するためのグローバル戦略と経営管理スキームの再構築が求められます。
そのためには、現地市場の実態把握や人材・パートナーとの信頼関係構築といった"地に足のついた準備"が不可欠です。
短期的な成果を追うのではなく、中長期の視点で自社らしいグローバル経営の在り方を描くことこそが、持続的成長への第一歩となります。
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト